貧困
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/02 00:14 UTC 版)
この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。 |
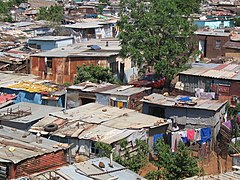


注釈
- ^ 国際連合腐敗防止条約を含めて条約は批准しない国に対して法的拘束力を持たないことも要因の一つ。
出典
- ^ a b 世界銀行 (2024年3月28日). “Poverty headcount ratio at $2.15 a day (2017 PPP) (% of population)” (Excel). 2024年4月21日閲覧。
- ^ “March 2024 global poverty update from the World Bank: first estimates of global poverty until 2022 from survey data(世界銀行による2024年3月の世界貧困最新情報: 調査データからの2022年までの世界における貧困の最初の推定)”. 世界銀行 (2024年3月26日). 2024年4月21日閲覧。
- ^ 世界銀行 (2024年3月28日). “Poverty headcount ratio at $3.65 a day (2017 PPP) (% of population)” (Excel). 2024年4月21日閲覧。
- ^ 世界銀行 (2024年3月28日). “Poverty headcount ratio at $6.85 a day (2017 PPP) (% of population)” (Excel). 2024年4月21日閲覧。
- ^ 2016 Global Hunger Index chapter2 Global, regional, and national trends, International Food Policy Research, (2016-10)
- ^ a b c d Healthy life expectancy (HALE) at birth, WHO, (2020-12-04) 2021年3月15日閲覧。
- ^ 国際連合開発計画 (8 September 2022). Human Development Index (HDI) (Excel) (Report). 2022年11月18日閲覧。
- ^ 関根由紀「日本の貧困--増える働く貧困層 (特集 貧困と労働)」『日本労働研究雑誌』第49巻第6号、労働政策研究・研修機構、2007年6月、21頁、NAID 40015509240。
- ^ a b 独立行政法人農業環境技術研究所「情報:農業と環境 No.104 (2008年12月1日) 化学肥料の功績と土壌肥料学」
- ^ 山野良一(2014)『子どもに貧困を押しつける国・日本』、光文社(光文社新書)、p.31
- ^ 男女共同参画社会の形成の状況内閣府男女共同参画局
- ^ 石井光太『絶対貧困-世界最貧民の目線』光文社 2009年 ISBN 9784334975623 pp.35-38.
- ^ “World Economic Outlook Database, October 2020” (英語). IMF (2020年10月). 2021年3月16日閲覧。
- ^ “2021 CIA World Fact Book Infant mortality rate” (英語). CIA (2021年). 2021年3月16日閲覧。
- ^ 教育における差別を禁止する条約
- ^ ジェフリー・サックス『貧困の終焉――2025年までに世界を変える』、鈴木主税・野中邦子共訳、早川書房、2006年。
- ^ 原田泰・大和総研 『新社会人に効く日本経済入門』 毎日新聞社〈毎日ビジネスブックス〉、2009年、33頁。
- ^ a b How globalization begets inequalityS. Garlock, Harvard Magazine, March-April 2015
- ^ ポール・コリアー『最底辺の10億人: 最も貧しい国々のために本当になすべきことは何か?』中谷和男訳、日経BP社、2008年
「貧困」の続きの解説一覧
品詞の分類
- >> 「貧困」を含む用語の索引
- 貧困のページへのリンク
