マリアナ沖海戦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/22 07:32 UTC 版)
勝敗の要因
小沢治三郎司令部
指揮官の能力
本作戦の敗因の一に、機動部隊の長官である小沢中将の能力不足が挙げられている。 機動部隊の田中正臣航空参謀によれば、小沢中将には飛行機に対する知識が絶対的に不足しており、艦隊司令官でなく艦長が持っている程度の知識であり、訓練や性能の意味もよく知らなかったうえ、それを補佐すべき幕僚には小沢中将に意見できるような人物がいなかったという[61]。また、小沢中将は本作戦の際に旗艦に軍楽隊を乗せ、どう間違っても勝ち戦だと確信している気運があったという[62]。二航戦の奥宮正武航空参謀は、同海戦の敗北後に小沢司令部の高級幕僚から「勝敗は時の運」という言葉を聞き、それが当時の小沢司令部の空気だったという[63]。また、「マリアナ沖海戦での小沢司令長官の戦法(アウトレンジ戦法)は良かったが、飛行機隊の実力がこれに伴わなかったという説があるが、私はこれに賛成出来ない。第一線部隊の指揮官の最大の責務は戦闘に勝つか、払った犠牲にふさわしい戦果を挙げることであるからである」と述べている[64]。
第一戦隊司令官宇垣纏中将は、1944年4月末に「大鳳」で行われた図上演習を部外者として見学したが[65]、第一機動部隊に対し「生死の岐るゝ本圖演に於て、徒らに青軍に有利なる経過あるは指導部として注意すべき點なり」と苦言を呈している[66]。5月5日の「大鳳」での図上演習では「全體を通じ見るにKdF司令部は手前味噌の感無き能はず。戦は一人角力に非ず。噴戒を要す」と怒りを示している。
アウトレンジ戦法
本作戦で小沢長官が採用したアウトレンジ戦法は、成果をあげずに多大な犠牲を払うこととなり、連合軍からは「マリアナの七面鳥撃ち(Great Marianas Turkey Shoot)」と揶揄される結果になった。
この戦法に対しては、反対意見もあった。航空本部部員角田求士は「海戦後ある搭乗員から出撃前の打ち合わせ会で「現在の技量では遠距離攻撃は無理だと司令部と議論をした」という話を聞いた」という。軍令部部員の源田実は、「自分はアウトレンジには反対でリンガに出張した時、第一機動部隊司令部に忠告してきた。その理由は、航空攻撃の時発進後適当なウォーミングアップが必要で、発進後三十分ないし一時間が適当である。これより早くても遅くても不適当である。従って発進距離は200浬、多くとも250浬以内が適当である」という。第二航空戦隊参謀奥宮正武は「大鳳の打ち合わせでアウトレンジに対する反対意見を述べた。それは当時の練度では自信がなかったからである。ただし意見を述べただけで議論はしなかった」という[11]。奥宮参謀は敢えて議論をしなかったことについて「本件については既に作戦前から小澤司令部の参謀達とよく話してあったが、彼等は母艦航空戦を理解しておらず、ましては理解も出来無かった…と言うより聞く耳を持たなかった」「そんな経緯もあり、大鳳での打ち合わせという最終段階において、その様な議論をすることは利益よりも害が多いから」と述べている[67]。
一方で、機動部隊司令部は反対意見の存在を否定している。小沢長官は戦後、防衛庁戦史室でのインタビューに「彼我の兵力、練度からしてまともに四つに組んで戦える相手ではないことは百も承知。戦前の訓練、開戦後の戦闘様相を考え、最後に到達した結論は『アウトレンジ、これしかない』であった。戦後になってアウトレンジは練度を無視した無理な戦法とか、元から反対だったとか言い出した関係高官が出て来たが、当時の航空関係者は上下一貫してこの戦法で思想は一致していた。」と語っている[68]。先任参謀大前敏一も反対意見を聞いたことがないという[11]。
しかし、結果的にはこのアウトレンジ戦法は無謀であった。ただでさえ、太平洋の真っ只中において母艦から発艦した艦載機が、敵艦隊攻撃後、再び母艦に戻ってくることは、敵に到達する以上に難しいのに、その距離が今までの作戦よりずっと長大だったのである。特に航法担当者のいない単座機である零戦などは、味方機と離れてしまうと独力で戻ってくることは難しかった。そのため、洋上で機位を失し燃料切れで母艦に帰投できなかった母艦機も相当数あったと考えられている[14]。 また長距離飛行となるので、事前に索敵機が発見した敵艦隊の移動距離も大きくなるわけで、ましてや未錬成の搭乗員ではこれを発見するのは至難のわざであった。二航戦の奥宮航空参謀は、攻撃隊の前方に前路索敵(誘導)機を先行させ、この誘導機によって攻撃終了後、再び攻撃隊を母艦まで誘導することも期待されたが、結果的には、それらの効果は認められず、多数の未帰還機を出した[69]。 また、母艦の索敵機の一部は、緯度変更に伴う磁針の訂正をしておらず、第58任務部隊の位置を誤って報告した。その結果、日本艦隊は米機動部隊が二群いるものと取り違え、実際には米艦隊のいない方角に乙部隊を中心とした100機近い航空機を差し向けてしまった。これらの攻撃隊は、米艦隊に会敵できず引き返したが、それでも少なからずの未帰還機を生じさせている。また、一部はロタ島等にある日本軍飛行場に着陸する直前に攻撃されたりして損害を出した。
また、第一機動艦隊の母艦艦載機が、タウイタウイ入泊後に各種訓練ができなかったこともアウトレンジ作戦失敗の要因であった。編成の早かった一航戦艦載の第601海軍航空隊搭乗員は、リンガ泊地・シンガポール付近で約一ヶ月程の訓練を行ったが、タウイタウイ入泊後は2回しか訓練出来無かった。これらの原因としては、タウイタウイ近辺に、全艦載機を挙げて訓練する飛行場がなかった事、泊地自体が第一機動艦隊が全艦入泊した時点で一杯になり、泊地内で空母が母艦機の訓練を行なう事が出来無いほど狭かった事、タウイタウイ島周辺に米潜水艦が多数出没した為、泊地から出て訓練ができなかった事が挙げられる[注釈 23]。
編成が遅れた二航戦の第652海軍航空隊、三航戦の第653海軍航空隊は、内地で満足に訓練が出来無いままタウイタウイに直行した為、僅かに回航中に1回、入泊後5月18日と同31日の2回しか訓練を行えなかった。その為、二航戦の奥宮正武航空参謀は「タウイタウイでは“如何に練度を上げるかではなく”“如何にしてこれ以上、練度を下げないようにするか”に腐心した」という[71]。363空飛行長の進藤三郎は「その頃の搭乗員の練度は何とか着艦ができる程度、洋上航法や空戦はやっとこさ というくらいで、とても『アウトレンジ戦法』どころではなかった」という[72]。
艦攻等は攻撃が訓練の主体なので列機は指揮官機の後ろについて行く考えが強く、指揮官機が墜とされると、もうどちらへ行ってよいのかわからないものが多かった。練度は3分の2が通常の任務遂行に支障なく、残りの3分の1も平易な状況下で作戦可能であったが、特に練度が高くて距離的にも心配のないのは全部のうち二ないし三組だけであった[73]。652空飛行隊長岩見丈三によれば、分隊長以上の指揮官で訓練を補おうとしていたようだが、実際はうまくいかず、戦術行動などは机上訓練であったという。田中航空参謀によれば、タウイタウイでやるはずだった必要なウォーミングアップができずに戦闘指向が上がらなかったことが最大の原因であるという。奥宮二航戦参謀によれば、練度が落ちて索敵に自信がなく、発見しても命中できるかどうか疑問であったという[74]。
戦力の格差
航空戦力
航空戦力には決定的な差があり、日本側が498機に対し、アメリカ側は901機であった。 母艦部隊は1943年末から1944年初頭までに南東作戦で消耗しており、訓練もほぼ実施できなかったので本作戦を行うには練度不足であった[59][75]。
もう一つの航空戦力である基地航空部隊の第一航空艦隊は作戦前の消耗戦でその多くを失い、練度も芳しくなかった。 一航艦は将来の主戦力として期待されて錬成が続けられていたものだが、練成途中にクェゼリン、ルオットの玉砕が起こり、1944年2月15日に連合艦隊への編入が決められた[76]。さらにトラック被空襲によって一航艦の実戦投入が早まった。一航艦整備参謀山田武中佐によれば「トラック被空襲により予定外の五三二空、一二一空等の実動全力のマリアナ方面投入が命ぜられたが、それまでの内地における訓練の実体は各隊訓練のみで、航空艦隊設立の主旨である大兵力の機動集中は一部の部隊(二六一空、七六一空)のみで実施されていた状況である。全般の練度については、一航艦のマリアナ展開が時期過早と考えられ、五二一空、一二一空に至ってはマリアナに出ていってから訓練する方針であり、自分は訓練状況をよく知り過ぎていた関係からとても自信を持ち得なかった」という[77]。
第一航空艦隊は2月23日マリアナ進出時にマリアナ諸島空襲を受けた。淵田美津雄参謀は、戦闘機が不十分なこと、進出直後で攻撃に成算がないこと、消耗を避けることを理由に飛行機の避退を一航艦長官角田覚治に進言したが、角田長官は見敵必戦で迎撃を実施し、最精鋭でもあるほぼ全力の90機を失った[78]。その後も増援された戦力の消耗を続けた。
直前の渾作戦によって攻撃集団(一航艦)の集中が遅れ、基地航空部隊は逐次消耗し、決戦に策応できなかった[59]。5月27日、米陸軍主体の連合軍はビアク島へ上陸を開始、この方面は絶対国防圏からも外れ、作戦命令方針にも一致しなかったが、連合艦隊が独自の判断で決戦兵力の第三攻撃集団を投入した[16]。29日、渾作戦が実施され、決戦兵力の第二攻撃集団もハルマヘラ島方面に移動させた[17]。5月11日マリアナ空襲を受け、連合艦隊は第二攻撃集団をヤップ島に戻したものの、第一攻撃集団はパラオ空襲の被害が大きく、第二攻撃集団ではデング病が蔓延、第三攻撃集団はすでに消耗し、第一航空艦隊はすでに作戦協力が不可能な状態にあった[31]。一連の戦いで稼動機を全て失った第732海軍航空隊は戦闘詳報で「小兵力を駆って徒に無効なる攻撃を続け、兵力を損耗し尽くすに及んで已むに至るが如き作戦指導は、適切とは称し難し。耐久的戦勢に於いては、見敵必戦策なき無理押しを反覆せず、兵を養い機を見て敵の虚に乗じ、戦果を発揚する如くすべきなり」と評した[79]。この様な事情から第一航空艦隊で作戦に参加できたのは100機程度であり、邀撃戦を少数かつ分散した状況で実施し、期待されていたような総合威力を発揮することはできなかった。
対空防御力
本海戦における攻撃力の主は航空戦力であったが、それならば防御力の主は対空防御力となる。その対空防御力の日米差は、航空攻撃力以上の差があった。米機動部隊に艦載されていた戦闘機はすべてF6Fであり、日本の零戦に優位はなく、陸上攻撃機も性能不足で、空襲への迎撃態勢も米軍がレーダー・無線電話・CIC(戦闘指揮所)などを使用、導入して戦闘機を有効活用し、高角砲の対空射撃にVT信管を開発、使用していたのに対し(上述の通り対空砲火による損害はほとんどなくかつVT信管の使用率も20%程度で本海戦におけるVT信管による損害と言えるものは微々たるものであった。)、日本側は従来の防空方法のままであった。これは潜水艦など他の兵器にも言えることで、兵器の進歩性で日本軍はアメリカ軍に大きな差をつけられたまま本海戦を迎えたのであった[59]。
アメリカ海軍機動部隊は、レーダーとCICによる航空管制を用いた防空システムを構築していた。潜水艦からの報告で日本艦隊の動向を掴んでいたアメリカ機動部隊・第58任務部隊は、初期のレーダーピケット艦と言える対空捜索レーダー搭載の哨戒駆逐艦を日本艦隊方向へあらかじめ約280km進出させておいて、日本海軍機の接近を探知した。そしてエセックス級航空母艦群に配備されていた方位と距離を測定するSKレーダーと高度を測定するSM-1レーダーの最新型レーダーで割り出した位置情報に基づいて日本側攻撃機編隊の飛行ベクトルを予測し、400機にも及ぶF6F ヘルキャットを発艦させて前方70〜80kmで、日本側編隊よりも上空位置で攻撃に優位となる高度約4,200mで待ち受けさせた。
進出させた哨戒駆逐艦や他空母など自艦と同じ最新型レーダーを搭載した艦を含む傘下各艦隊、戦闘空域近くを飛行する早期警戒機、早期警戒管制機の元祖といえる高性能レーダーと強力な無線機を搭載した特別なTBMなどから各々探知した日本機編隊の情報が、第58任務部隊旗艦のエセックス級航空母艦「レキシントン」のCICに伝えられた。
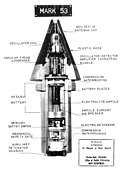
当時のCICは、まだ戦闘に関する情報をほとんど完全な手動で処理、統合、分析を行なうだけで、戦闘機誘導所がCICからの情報をもって空中待機中の戦闘機隊を無線で、向かってくる日本機編隊ごとに振り分けその迎撃に最も適した空域へ管制し、交戦開始後は各戦闘機隊の指揮官が現場指揮を執り、圧倒的多数で飛躍的に向上していた戦闘機性能とそれらを生かした戦法により、熟練パイロットがほとんど失われていた日本機隊に対し、ほとんど一方的な勝利を収めた。これが「マリアナの七面鳥撃ち」(原語:the Great Marianas Turkey Shoot)と呼ばれたのは、もともとアメリカの俗語で楽な仕事を意味する「七面鳥撃ち」(原語:Turkey Shoot)[80]という表現が、米国で軍関係者の言葉として「圧倒的実力差のあるワンサイドゲーム」の意味で用いられたためである[81]。
また、1943年の末頃から、対空砲弾が命中しなくても目標物近く通過さえすれば自動的に砲弾が炸裂するVT信管を高角砲弾に導入した。この結果、従来の砲弾に比べて対空砲火の効果は3倍に跳ね上がった。アメリカ軍は概ね3倍程度と評価している。なお、マリアナ沖海戦におけるアメリカ艦隊の対空砲火のスコアは戦闘機の迎撃を突破して艦隊上空に到達できた日本機が少なかったこともあり、VT信管弾や40mmボフォースなど全てを合計しても19機(アメリカ側確認スコア。当然誤認を含むと思われる)に過ぎなかった。また1943年に開発されたばかりのVT信管はマリアナ沖海戦時点では製造が間に合っておらず、アメリカ艦隊が発射した全高角砲弾のうちVT信管弾が占める割合は20%程度であったが、圧倒的な対空砲火の弾幕とあいまって既に残り少なくなった日本機に対し着実に効果を発揮した可能性は高い。
日本軍でも、アメリカ艦隊の対空防御能力を「敵艦艇の対空火力は開戦初期はバラバラ、その後火ぶすまに変わり、今やスコールに変わった」として、これまでのような方法でアメリカ空母を攻撃しても成功は奇蹟に属すると考えるようになった[82]。
アメリカ軍の指揮
勝利を得たアメリカ軍だが、スプルーアンスの作戦指揮については消極的であるとの批判がなされた。6月18日に攻勢に出なかったことや、20日になるまで西方への進撃を行わなかったことなどが指摘され、航空戦の専門家でないスプルーアンスが指揮官だった点も問題視された[83]。これに対し戦史家のサミュエル・モリソンはスプルーアンスの戦術指揮は正しかったと主張している。サイパン攻略の支援という任務を負っていたことから、日本の航空部隊により大きな打撃を与えることは困難であった。また、西進していれば、何隻かの艦艇が失われる結果になっただろうと反論している[83]。
モリソンは、どちらかといえば19日に夜間索敵が行われず、日本艦隊発見が遅れたことを問題視している。19日夜の段階で日本艦隊を発見できれば、翌20日に早朝から攻撃が可能であったはずだと指摘する。ただ、ミッチャーが夜間捜索をしなかったのは、搭乗員の疲労が激しかったことへの配慮に基づくものであったと擁護している[83]。
注釈
- ^ この訓練方法が問題となり、美濃部は第301海軍航空隊司令八木勝利中佐から飛行隊長を更迭されている[27]。
- ^ ミッドウェー海戦の際にはわずか7機であったものを、戦訓により索敵力を強化したものである。
- ^ 21型に現地改修で懸吊架装備をつけて戦闘爆撃機としたタイプであり、後年量産された62型(52丙型の胴体下に250kg爆弾の懸吊架装備をつけた戦闘爆撃機型)とは別機体
- ^ 『いざゆけ!ゼロ戦 最強の戦闘機、激闘の伝説 スーパー戦闘機で知る太平洋戦争 ゼロ戦は無敵だった!』(KKベストセラーズ、2007年)230頁によると、「8時20分、前衛部隊の戦艦大和の艦橋で第1次攻撃隊127機が高度4000メートルで前衛部隊に近づいてくるのを発見したが、無線封鎖中の前衛部隊ではこの100機を超える編隊が敵か味方か、判別できなかった。日本海軍では飛行機は味方軍艦上空を飛ばないことになっており、重巡洋艦高雄が味方識別合図を要求するため高角砲4発射ち上げたが、編隊は無反応のまま艦隊の真上に向かって距離1万5千メートルまで接近。大和は敵編隊とみなして全艦に左45°一斉回頭と対空射撃の緊急命令を出し、各艦は回頭と発砲を始めた。日本機編隊は慌てて翼をバンクさせて味方だと知らせたのだが、4機も被弾して落ちていった。」
- ^ 1航戦若しくは2航戦所属機を収容したと思われる
- ^ 各空母への振り分けは次の通り。大鳳:零戦五二型20機、彗星一一型10機、九九式艦爆8機、天山一二型13機、二式艦偵3機。翔鶴:零戦21機、天山12機、彗星18機、二式艦偵10機、九九式艦爆3機。瑞鶴:零戦21機、天山12機、彗星18機、二式艦偵10機、九九式艦爆3機
- ^ 但し6月8日風雲沈没時に戦死
- ^ 但し6月8日に沈没
- ^ 但し6月9日に沈没
- ^ 各空母への振り分けは次の通り。隼鷹:零戦27機、彗星9機、九九艦爆9機、天山6機。飛鷹:零戦27機、彗星9機、九九艦爆9機、天山6機。龍鳳:零戦×21機、天山×11機
- ^ 6月8日の春雨沈没時に白浜政七駆逐隊司令が戦死し後任は未着任
- ^ 但し6月15日に油槽船清洋丸と衝突して沈没
- ^ 正式編成は海戦後の8月15日
- ^ 各空母への振り分けは次の通り。瑞鳳:零戦21機、天山9機。千歳:零戦21機、九七艦攻9機。千代田:零戦21機、九七艦攻9機
- ^ 6月9日に早波が沈没し折田大佐が戦死。15日付で玉波艦長の青木久治大佐が隊司令に赴任
- ^ 但し6月9日に沈没
- ^ パラオより合流、19日に分離
- ^ タウィタウィで対潜掃討中触礁損傷により全力発揮不能、第二補給部隊護衛へ異動となる
- ^ 海防艦はギマラスで待機。
- ^ 公刊戦史「潜水艦史」による
- ^ アイランドの煙突に命中するも、航行に支障無し。
- ^ 500ポンド爆弾を艦橋後部のマスト付近に命中したとしているが乗組員の回想では被弾無し、至近弾によるスプリンターを直撃弾と勘違いした可能性有り。
- ^ タウイタウイに閉じ込められた原因としては潜水艦の跋扈が上げられる。泊地を出た途端雷撃される事もあり、そのため、護衛の駆逐艦が損耗した。そもそもタウイタウイ島と、その周辺海域は、南シナ海で通商破壊を行なう米潜水艦航路の途中にあった。(しかし、タウイタウイは結局不運な選定であったことを証明した。当時、ニューギニアにおいて入手した、日本側書類によって、新しい日本の航空艦隊の出現とその進出位置が明らかになると、米潜水艦が大挙してセルベス海やフィリピン諸島周辺に集中行動したので、小澤部隊は訓練や演習の為に錨地外に出動することが殆ど出来無くなった。)[70]。
出典
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦付録
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦331頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦304-305頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦336頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦323-325頁
- ^ 堀栄三『大本営参謀の情報戦記』文春文庫128頁、戦史叢書12マリアナ沖海戦326-327頁
- ^ a b 戦史叢書12マリアナ沖海戦353頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦354頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦324-325頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦388-389頁
- ^ a b c 戦史叢書12マリアナ沖海戦390頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦432-433頁
- ^ モリソン(2003年)、286頁。
- ^ a b NHK『証言記録 兵士たちの戦争「マリアナ沖海戦 破綻した必勝戦法」』
- ^ モリソン(2003年)、287頁。
- ^ a b 戦史叢書12マリアナ沖海戦479頁
- ^ a b 戦史叢書12マリアナ沖海戦451頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦480頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦327-328頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦484頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦515頁
- ^ ブュエル 2000, p. 402.
- ^ 井手次郎 1992, pp. 27–28
- ^ a b 戦史叢書12 1968, p. 527
- ^ a b 伊沢 1975, p. 139
- ^ 御田重宝 1991, 電子版, 位置No.2946
- ^ 渡辺洋二 2003, p. 40
- ^ “Operation Forager and the Battle of the Philippine Sea”. Naval History and Heritage Command. 2022年1月21日閲覧。
- ^ “Operation Forager and the Battle of the Philippine Sea”. Naval History and Heritage Command. 2022年1月21日閲覧。
- ^ 戦史叢書12 1968, p. 304
- ^ a b 戦史叢書12マリアナ沖海戦524-525頁
- ^ a b 戦史叢書12マリアナ沖海戦530頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦538頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦389-390頁
- ^ モリソン(2003年)、284-285頁。
- ^ モリソン(2003年)、290-291頁。
- ^ a b モリソン(2003年)、292-293頁。
- ^ 草鹿 1979, p. 260.
- ^ a b 「戦闘詳報.第1機動部隊 あ号作戦(653空.第1機動艦隊司令部.千歳.千代田)(1)」第35画像
- ^ a b #小板橋見張員p.84、著者は当時愛宕航海部操舵手。
- ^ a b #小板橋見張員p.85
- ^ 「昭和19年6月20日 軍艦利根戦闘詳報 第7号(あ号作戦中対空戦闘に対する分)」第11-12画像、安永弘『死闘の水偵隊』344頁、筑摩所属偵察機乗員。山本佳男『巡洋艦高雄と共に』135頁、三連装機銃射手。
- ^ #艦爆隊長p.168
- ^ #艦爆隊長p.169
- ^ #艦爆隊長p.170
- ^ #艦爆隊長p.171
- ^ #艦爆隊長p.176
- ^ 「昭和17年6月1日~昭和19年6月30日 あ号作戦戦時日誌戦闘詳報(1)」第56画像
- ^ 「昭和19年6月20日〜昭和19年7月10日 第61駆逐隊戦闘詳報(2)」第1画像
- ^ 「昭和19年6月20日〜昭和19年7月10日 第61駆逐隊戦闘詳報(2)」第11-12画像
- ^ 「昭和19年6月20日〜昭和19年7月10日 第61駆逐隊戦闘詳報(3)」39頁
- ^ 「昭和19年6月20日〜昭和19年7月10日 第61駆逐隊戦闘詳報(3)」40頁、45-46頁、「昭和19年5月1日〜昭和19年10月31日 特設運送船日栄丸戦時日誌戦闘詳報(3)」8頁
- ^ 「昭和17年6月1日~昭和19年6月30日 あ号作戦戦時日誌戦闘詳報(1)」第58画像
- ^ 池田清『最後の巡洋艦矢矧』(新人物往来社、1998)、85頁
- ^ #小板橋見張員p.88
- ^ #小板橋見張員p.89
- ^ 昭和19年3月1日~昭和19年11月15日 第1機動艦隊戦時日誌12~28画像
- ^ 「戦闘詳報.第1機動部隊 あ号作戦(653空.第1機動艦隊司令部.千歳.千代田)(1)」第49-51画像
- ^ a b c d 戦史叢書12マリアナ沖海戦636-638頁
- ^ 辻田真佐憲『大本営発表』幻冬舎新書192-194頁
- ^ 吉田俊雄『指揮官たちの太平洋戦争』光人社NF文庫314-315頁
- ^ 吉田俊雄『指揮官たちの太平洋戦争』光人社NF文庫316頁
- ^ 『太平洋戦争と十人の提督』学研M文庫頁289-290頁
- ^ 『太平洋戦争と十人の提督』(617頁より)
- ^ #戦藻録(九版)319頁
- ^ #戦藻録(九版)320頁
- ^ 『真実の太平洋戦争』『太平洋戦争と十人の提督』より。
- ^ 田中健一「マリアナ沖海戦 作戦指導批判に異論あり」『波濤』110号 1994年1月
- ^ 『真実の太平洋戦争』(第二章 数多い誤認と誤解 2 夢に終わったアウトレンジ戦法より 157-158頁)
- ^ ニミッツの太平洋海戦史 太平洋戦争と潜水艦 269p/372p〜375pより
- ^ 『日本はいかに敗れたか 上』より
- ^ 神立尚紀『零戦最後の証言2』光人社NF文庫、pp.113f
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦379頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦379-380頁
- ^ 川崎まなぶ著『マリアナ沖海戦 母艦搭乗員 激闘の記録』(海軍が新規搭乗員の大量養成・母艦搭乗員の急速錬成に努力を払ったので、本海戦に参加した全母艦搭乗員の平均飛行時間は、開戦時〜南太平洋海戦までと比べて遜色ないレベルであったという指摘だが、飛行時間の計算は在籍年月から推計したもので根拠に欠ける)
- ^ 戦史叢書71大本営海軍部・聯合艦隊(5)第三段作戦中期207頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦411頁
- ^ 戦史叢書12マリアナ沖海戦55、78頁
- ^ 内藤初穂『戦艦大和へのレクイエム 大艦巨砲の技術を顧みる』(グラフ社、2008)185頁
- ^ “turkey shootの意味・使い方”. (株)アルク. 2023年6月13日閲覧。
- ^ “turkey shootの意味”. NTTレゾナント. 2023年6月13日閲覧。
- ^ 戦史叢書 41 P.110
- ^ a b c モリソン(2003年)、298-299頁。
固有名詞の分類
- マリアナ沖海戦のページへのリンク