汚職を追った「はみ出し者」二課刑事たち ぶつかった警察組織の変貌
ドラマ化決定『石つぶて』を語り尽くす〈「これは言えないカネです。これをしゃべったら殺されます」
「だから、何のカネなんだ」
「あれは領収書がいらないカネなんです……。総理の外遊時の経費です」
総理の? 領収書がいらない経費なんてあるのか。
大変なカネを見つけてしまった。下手すると、俺たちが政府を転覆させるのか。〉
『しんがり 山一證券 最後の12人』などで知られるノンフィクション作家、清武英利氏。その最新作『石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの』の舞台は、警視庁捜査二課。
冒頭のシーンは2001年に発覚した「外務省機密費流用事件」の取り調べの様子を描いたもので、日本社会を揺るがせた事件を掘り起こした名もなき刑事たちの実像に迫っている。
今秋、WOWOWでドラマ化されることが、早くも発表された本作。いま、なぜ「二課刑事」(ニカデカ)を描くのか。清武氏に聞いた。
「なんかおかしいな」から始まった
――『石つぶて』で描かれるのは、2001年に発覚した、外務省機密費流用事件です。容疑者は「ノンキャリの星」と呼ばれた職員でしたが、着服したカネで次々と愛人を作り、競走馬を何頭も所有していた。
主人公である警視庁刑事部捜査二課の捜査員たちは、機密費という「国家のタブー」に挑み、地道な裏付け捜査と職人技を駆使した取り調べを繰り広げます。
現実に起こった出来事とは思えないほど生々しく、衝撃的な内容ですが、なぜいま、捜査二課の刑事たちを描こうと思ったのですか。
清武 私は新聞の社会部記者として警視庁を担当し、なかでも当時の部署名で言えば、二課と四課(現在は組織犯罪対策課に改組)に出入りして、取材を重ねてきました。
刑事ドラマなどによく登場する捜査一課は殺人や強盗などを扱う部署ですが、知能犯を扱う二課が看板にするのは「サンズイ」。これは「汚職」の「汚」の文字の部首をとった言い方です。
二課刑事のなかには、自分たちを「瀆職刑事」(とくしょくけいじ)と呼ぶ人もいます。「瀆職」とはつまり、公務員や政治家など公職にある者が、その職務を冒瀆する行いを指します。
殺人は直接的に人を殺す犯罪ですが、汚職というのは内側からゆっくりと社会を殺す。そんな汚職を、自分たちがしっかりと検挙していくことによって、公務員や政治家の腐敗を抑止する。ひいては、日本社会を守っていく。私が出入りしていた当時の二課刑事たちからは、そういう「瀆職刑事」としての誇りが、言動の端々から感じられたものです。
その後、私も新聞社で管理職になり、二課との距離は遠くなっていたのですが、ノンフィクション作家として活動するようになった2010年代になって、ふと、「なんか最近おかしいな」と感じたのです。
「最近、汚職って摘発されていないな。なぜだろう?」と。
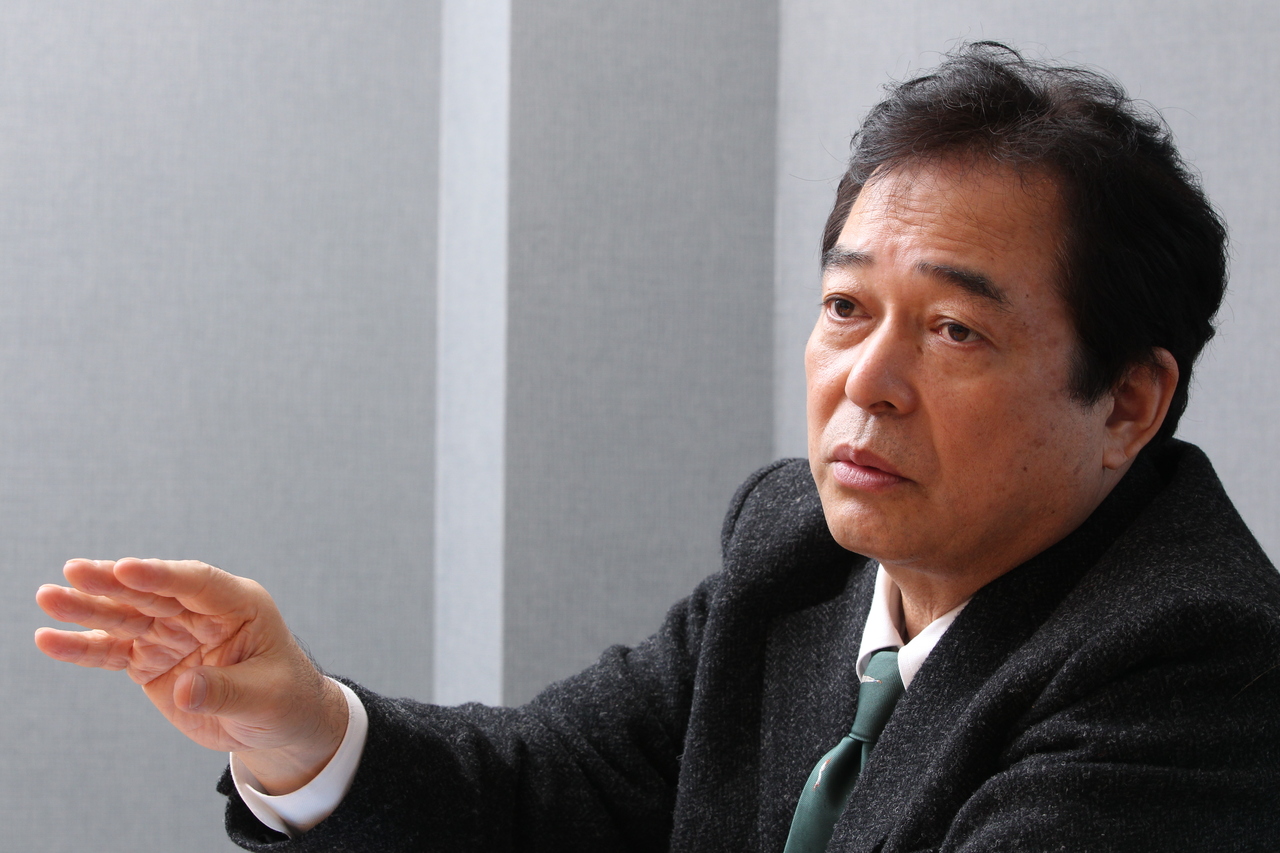 「なぜ」から取材が始まると語る清武氏
「なぜ」から取材が始まると語る清武氏
実際、汚職事件の検挙数は近年、激減しています。2000年代前半には年間10件を超えることもあった警視庁の贈収賄事件の摘発数は、2005年以降、年間5件ほどに落ち込み、2014年にはとうとう「摘発ゼロ」という記録を作ってしまいました。こうした傾向は警視庁だけではなく、全国の道府県警や検察庁を見ても同じです。
「なぜ、そんなことになっているのか?」という疑問が膨らみ、かつて取材対象だった二課刑事の人脈をたどり、疑問の答えを求めて訪ね歩いたんです。
