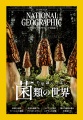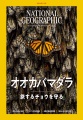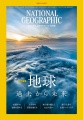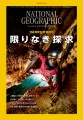「中世の教会を飾るステンドグラスは下部ほど厚い」。化学の授業ではその理由を、ガラスが長い時間をかけて液体のように下方へ流動するからだと習う。ところが最近、ガラス形成の仕組みに関する基礎研究を行っていたグループが、類似した特性を持つ琥珀(こはく)の分子構造について、数千万年の間ほとんど変化しないという事実を突き止めた。 研究結果を発表したのは、アメリカのテキサス工科大学教授で、化学工学が専門のグレゴリー・マッケナ(Gregory McKenna)氏の研究グループ。マッケナ氏によると、「2000万年間の密度変化は、わずか2.1%だった」という。
◆琥珀はガラスと同じ非晶質
木の樹脂が化石化した琥珀は、規則的な原子配列が見られない非結晶性の物質(非晶質)だ。
アメリカ、ウィスコンシン大学の実験化学者マーク・エディガー(Mark Ediger)氏によると、「水晶のような結晶性の物質(結晶質)では、すべての原子が規則正しく配列しているので一部分の性質がわかれば全体を推測できる。それに対してガラスのような非晶質には、規則性がほとんどない」という。
同じ非晶質の琥珀の特性には類似点が多く、ガラスの研究に応用されることになった。
マッケナ氏らの主要な研究テーマは、“ガラス転移”という現象である。特定の温度に達した物質が、ゴムのように柔らかい状態から硬くて割れやすい状態へと急激に変化する現象で、長年研究されているが未解明な点が多い。例えば、状態変化する際に急速に流動性を失う理由などは、依然解明されていないという。エディガー氏は、「どのように考えるのが最善なのか見当がつかない」と語る。
◆広義の"ガラス"
ガラスと言えば、ケイ酸塩を主原料としている窓などに使われる透明な物質を思い浮かべるだろう。科学の分野では、より広く非晶質(アモルファス)の固体はすべてガラス状態と見なされる。その意味では、プラスチックも金属もガラスに変化させることができる。
マッケナ氏らはガラス転移現象に関する理解をより深めるため、2000万年前のドミニカ産琥珀でいくつかの実験を行った。
その1つが応力緩和実験で、棒状の琥珀にさまざまな温度下で引張応力を加え、その間に琥珀が元の状態に戻ろうとする力が減少する割合を測定する。琥珀内の分子の振舞いに関する手掛かりが得るのが目的だ。
琥珀棒にひずみを与えるためには一定の力が必要となるが、力が消失するまでの時間を測定すれば、琥珀内の分子がどの程度素早く移動できるかがわかるとエディガー氏は説明する。
物質がガラス状態に固化するときの温度は、その物質が過去にどの程度の時間をかけて冷却されたのかに依存する傾向がある。何千年も前の琥珀を使うと、常温下でしかも緩慢にガラス転移現象を起こすことができるのだという。
時間をかけて冷却された物質ほどガラス状態に変化する温度は低くなる。ただエディガーの説明によれば、「10倍の時間をかけて液体を冷却したとしても、固化する温度はごくわずか低くなるだけだ」という。
2000万年前の琥珀に着目した理由がここにある。いわば膨大な時間をかけて冷却されたガラスであり、実験室で再現することは到底できない。
「固化する温度は相当低い。通常の琥珀であればガラス状態にある常温下でも、液体の状態にすることができる。この物質が持つさまざまな特性を解明できれば、ガラスが形成される仕組みについてより多くの知見を得ることができるだろう」。エディガー氏はそう語る。
◆研究は続く
マッケナ氏らの研究グループは既に、今回よりさらに古い2億2000万年前、三畳紀の琥珀を使って同様の実験を行う準備を進めている。
「まだ初期段階にすぎないが、結論を得るまで続ける決意だ」とマッケナ氏は語る。
今回の研究結果は、「Nature Communications」誌オンライン版に4月30日付けで掲載されている。
Photograph by Carl D. Walsh, Aurora Photos/Corbis
◆琥珀はガラスと同じ非晶質
木の樹脂が化石化した琥珀は、規則的な原子配列が見られない非結晶性の物質(非晶質)だ。
アメリカ、ウィスコンシン大学の実験化学者マーク・エディガー(Mark Ediger)氏によると、「水晶のような結晶性の物質(結晶質)では、すべての原子が規則正しく配列しているので一部分の性質がわかれば全体を推測できる。それに対してガラスのような非晶質には、規則性がほとんどない」という。
同じ非晶質の琥珀の特性には類似点が多く、ガラスの研究に応用されることになった。
マッケナ氏らの主要な研究テーマは、“ガラス転移”という現象である。特定の温度に達した物質が、ゴムのように柔らかい状態から硬くて割れやすい状態へと急激に変化する現象で、長年研究されているが未解明な点が多い。例えば、状態変化する際に急速に流動性を失う理由などは、依然解明されていないという。エディガー氏は、「どのように考えるのが最善なのか見当がつかない」と語る。
◆広義の"ガラス"
ガラスと言えば、ケイ酸塩を主原料としている窓などに使われる透明な物質を思い浮かべるだろう。科学の分野では、より広く非晶質(アモルファス)の固体はすべてガラス状態と見なされる。その意味では、プラスチックも金属もガラスに変化させることができる。
マッケナ氏らはガラス転移現象に関する理解をより深めるため、2000万年前のドミニカ産琥珀でいくつかの実験を行った。
その1つが応力緩和実験で、棒状の琥珀にさまざまな温度下で引張応力を加え、その間に琥珀が元の状態に戻ろうとする力が減少する割合を測定する。琥珀内の分子の振舞いに関する手掛かりが得るのが目的だ。
琥珀棒にひずみを与えるためには一定の力が必要となるが、力が消失するまでの時間を測定すれば、琥珀内の分子がどの程度素早く移動できるかがわかるとエディガー氏は説明する。
物質がガラス状態に固化するときの温度は、その物質が過去にどの程度の時間をかけて冷却されたのかに依存する傾向がある。何千年も前の琥珀を使うと、常温下でしかも緩慢にガラス転移現象を起こすことができるのだという。
時間をかけて冷却された物質ほどガラス状態に変化する温度は低くなる。ただエディガーの説明によれば、「10倍の時間をかけて液体を冷却したとしても、固化する温度はごくわずか低くなるだけだ」という。
2000万年前の琥珀に着目した理由がここにある。いわば膨大な時間をかけて冷却されたガラスであり、実験室で再現することは到底できない。
「固化する温度は相当低い。通常の琥珀であればガラス状態にある常温下でも、液体の状態にすることができる。この物質が持つさまざまな特性を解明できれば、ガラスが形成される仕組みについてより多くの知見を得ることができるだろう」。エディガー氏はそう語る。
◆研究は続く
マッケナ氏らの研究グループは既に、今回よりさらに古い2億2000万年前、三畳紀の琥珀を使って同様の実験を行う準備を進めている。
「まだ初期段階にすぎないが、結論を得るまで続ける決意だ」とマッケナ氏は語る。
今回の研究結果は、「Nature Communications」誌オンライン版に4月30日付けで掲載されている。
Photograph by Carl D. Walsh, Aurora Photos/Corbis