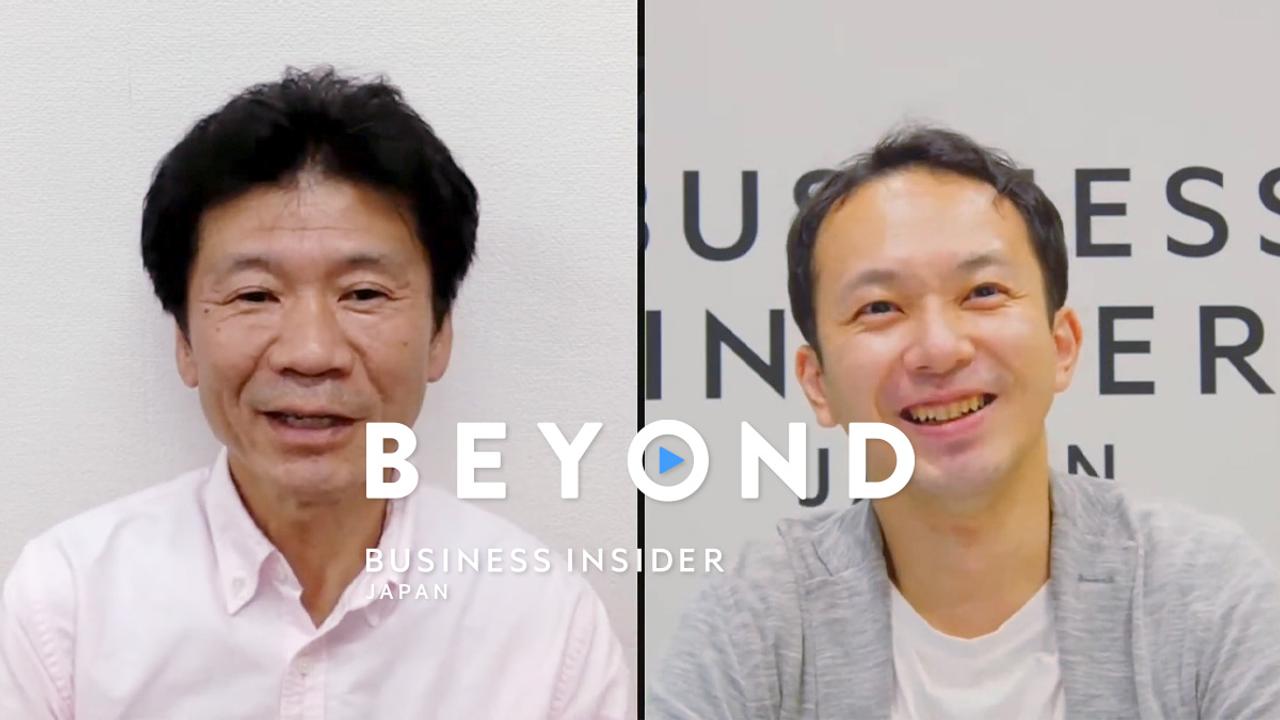「Beyond Sustainability 2022」の環境部門を受賞したリージョナルフィッシュ。CEOの梅川さん(左)とトークセッションを展開した。
収録画面をキャプチャ
持続可能な社会の実現に取り組む企業を表彰する、Business Insider Japan主催のアワード「Beyond Sustainability 2022」。2年目を迎えた2022年は、7月25〜29日の5日間にわたり、オンラインで「Beyond Sustainability Week」を開催した。
7月26日のday2は、「ノーベル賞受賞の技術が水産業の未来を救う」と題し、環境部門の受賞企業、リージョナルフィッシュのトークセッションを展開した。
リージョナルフィッシュのCEO、梅川忠典さんが語る新しい水産業のあり方とは?
ゲノム編集による品種改良と陸上養殖で世界をリードする同社の挑戦について、Business Insider Japanデスクの三ツ村崇志が聞いた。
日本が「世界ナンバーワンではない」現実
——リージョナルフィッシュはいわばテクノロジー系の企業ですが、梅川さん自身は大学で経営を学ばれたんですね。
梅川忠典さん(以下、梅川):はい。日本経済の発展につながる仕事がしたかったからです。経営学を選んだのは「日本の会社は技術で勝って経営で負けている。だから世界で戦えなくなった」と言われていたから。であれば、企業の経営を支えるために経営学を学ぼうと思ったんです。
——京都大学卒業後コンサルティングファームに就職し、数年後に転職されました。
梅川:コンサルティングファームで仕事をするうちに、もっと深く企業を支援したいと思うようになったんです。そんな中で「オープンイノベーションを通じて次世代の国府を担う産業を育成・創出する」というビジョンを掲げる産業革新機構と出合い、転職しました。
——産業革新機構に転職後、日本企業に対する印象は変わりましたか?
梅川:産業革新機構では日本の名だたる企業に資金提供をする仕事に携わりました。その中で感じたのは、日本の技術は必ずしも世界ナンバーワンではないということです。
——経営だけでなく、技術もナンバーワンではないと?
梅川:昔は確かに世界ナンバーワンだったんです。ただ、稼いだお金を次の技術にしっかり投資していくという循環が起きていなかった。だから技術的にも諸外国に負けていったんだと気付きました。
——それをどう捉えましたか?
梅川:それなら、もう既にある、世界ナンバーワンクラスの技術をもとに起業すれば、世界で戦える会社ができるかもしれない。自分が目指してきた「日本経済の発展に貢献する」という目標を実現できるかもしれないと思ったんです。

梅川さんが最初に立ち上げたのは昆虫食ベンチャー。そこから京大研究者らとの人脈が広がり、リージョナルフィッシュにつながった。
収録画面をキャプチャ
京都大学のベンチャープログラムが転機に
——起業の具体的なきっかけは?
梅川:技術を使ってイノベーションを起こすようなビジネスの創出を支援する、京都大学のプログラムに参加したことですね。2017〜2018年当時、私は東京・丸の内で働いていたのですが、会場が新丸ビルだったこともあり「これはいい!」と思って。
——当初は昆虫食に注目されたそうですね。
梅川:ちょうどその頃、急増する世界の人口に対してタンパク質が不足する時代が到来するという話が注目され始めていました。
——いわゆる“タンパク質危機”ですね。
梅川:タンパク質危機に備えるには、より少ない餌(エサ)で育つ食品の開発が必要になる。その意味で、昆虫はかなりエサが少なくても育つので、将来有望なのではないかと思ったんです。
——昆虫食ビジネスはその後どうなりましたか?
梅川:提案したビジネスプランが(プログラム内の投資家向けプレゼンで)優勝。それをもとに、プログラムで知り合った京大の先生たちと昆虫食のベンチャー企業を立ち上げました。
——当時はまだ産業革新機構に勤めていたんですか?
梅川:はい。昆虫食ベンチャーはまだ副業で、産業革新機構の仕事をしながら、京大の先生たちに開発をしていただく形で進めていました。
衰退する日本の水産業を「技術」で復活させたい
——昆虫食ベンチャーからリージョナルフィッシュ設立までには、何があったのでしょうか?
梅川:昆虫食ベンチャーの経営を通して京大の先生たちとのつながりが強まり、色々な技術を紹介してもらうようになっていきました。その中で出会った1人が、京都大学農学研究科の准教授、木下政人先生でした。
——リージョナルフィッシュの共同創業者兼CTOの木下さんですね。
梅川:木下先生はゲノム編集で肉の量を増大させたマダイなどを開発してきた方で、衰退し続ける日本の水産業を技術の力で何とかしたいというビジョンを持っていました。そこにとても共感したんです。
——実食もされたとか。
梅川:木下先生が品種改良したトラフグがすごく美味しくて。これは将来のタンパク源として行けるんじゃないかと思いました。
——それがリージョナルフィッシュ設立につながったわけですね。
梅川:その後、先生とも国際的な競争力やビジネス化について調査・検討した上で、昆虫食ベンチャーの代表を別の方に譲り、産業革新機構も退職して、木下先生とリージョナルフィッシュを創業しました。
——タンパク質危機対策としては昆虫食も伸びしろがあると思うのですが、水産物一本に絞ったのはなぜですか?
梅川:当時はまだ、食用昆虫の研究が始まったばかりの時期だったんです。でも、私は今ある技術で世界ナンバーワンクラスのビジネスを起業したかった。昆虫食より、木下先生が開発したシーズ(水産物のゲノム編集)のほうが私の思いに近いと感じました。

かつては世界一の水産大国だった日本はいまや8位に後退。「技術的に追いつかれやすい」水産業の構造に変革を起こしたい、と梅川さん。
収録画面をキャプチャ
——日本の水産業は衰退し続けているとのことですが、今どんな状況にあるのでしょうか?
梅川:この30年で世界の水産量(生産量)は倍増しました。ところが、世界1位の水産大国だった日本は3分の1に激減し、8位にまで後退しています。
日本は漁業権の関係もあって、売り上げが1億円未満という小規模事業者がほとんど。また、技術は基本的にオペレーションに関わるもので、研究開発(R&D)から生まれてきたわけではありません。
——それはどんな問題をもたらすのでしょうか。
梅川:技術的に追いつかれやすい構造だということです。つまり、人件費や土地代が安い国でやったほうがいいという話になっていく。実際、日本は収益を上げられずに担い手が不足、(水産業で成り立っていた)地域もどんどん衰退していきましたが、(低コストの)東南アジアの水産業はものすごく伸びています。
実は「養殖モノは存在しない」水産物

リージョナルフィッシュが開発したゲノム編集トラフグ(22世紀ふぐ)の刺し身。
撮影:山﨑拓実
——水産業にビジネスチャンスがあると考えた理由は?
梅川:水産物以外の食べ物、つまり農産物や畜産物に「天然種」はもはや存在しません。例えば、ブタは野生のイノシシを品種改良したものですし、イチゴだって野生のヘビイチゴを改良したもの。水産物だけが「天然モノ」なんです。
——養殖のフグやマグロもありますが、厳密な意味では養殖ではないと?
梅川:養殖といっても、水産物の場合はあくまで野生に存在していた種を、自然環境下で人が飼育しているという意味であって、豚やイチゴのように品種改良した種を人間が制御して育てているわけではありませんから。
——水産業はなぜ天然物だけだったのでしょうか?
梅川:卵から成魚にしてまた卵を生むという「完全養殖(※)」の技術を確立させるのが難しかったからです。世界で初めて完全養殖に成功した近大マグロ(※)も研究開始から30年以上という、相当な時間がかかったんです。
※完全養殖とは:人工的に孵化させた稚魚を成魚へと育て、その成魚に産ませた卵を再びふかさせて次世代の魚を生み出していくこと。どの工程でも天然資源に頼らずに生産が可能になる。
※近大マグロとは:近畿大学水産研究所が1970年に研究を開始し、2002年に世界で初めて完全養殖に成功したクロマグロ。
——リージョナルフィッシュは近大水産研究所と共同研究も進めてきましたね。
梅川:はい。完全養殖の技術を最も多く持っているのが日本であり、近畿大学。つまり我々のチームです。それが、我々が世界のトップランナーになれた理由です。
2倍速く成長し、エサを4割減らせる
——ゲノム編集にはどんなメリットがあるのでしょうか?
梅川:ゲノム編集の技術を使うと通常よりずっと速く品種改良できます。より強く、より生産性が高く、より美味しいといった種を開発し、天然の環境ではなく陸上の生け簀(す)で育てる。
人工的な環境であれば、海と違って、水温もpHも溶存酸素(水中に溶けた酸素)もコントロールできるので、開発スピードが圧倒的に違うんです。
——それがリージョナルフィッシュのビジネスモデルというわけですね。
梅川:そうです。ゲノム編集と陸上養殖「スマート養殖」を組み合わせたビジネスモデルの構築を目指しています。人間がコントロールすることで、環境負荷を抑え、必要な食べ物をもっと効率的に届けられると考えています。

「スタートアップはスピード感が大切」と話す梅川さん。まずは国内各地で地元の水産関係者と協力して各地のニーズに合った品種を開発、5年以内に東南アジア進出を目指す考えを明らかにした。
収録画面をキャプチャ
——具体的には、どのような課題やニーズに応えていけるのでしょうか?
梅川:グローバルに戦うための品種と地域ブランディングのための品種、この2軸で考えています。例えば速く成長するといった生産性の高さは、どこの世界でも必要とされています。
——地域ブランディングについては?
梅川:例えば、京料理では脂(あぶら)がそんなに乗っていなくても旨味のある魚が欲しいとか、この地域では生で食べることが多いから脂が乗っていたほうがいいとか。地域によって異なるニーズに基づいて品種改良し、それをキーに地域ブランディングをしていくことが可能です。
——陸上養殖というのは結構な手間暇がかかると思うのですが、コスト的にはどうなんでしょう?
梅川:我々がつくったトラフグは生産性(成長速度)が1.9倍、飼料(エサ)の量が4割減になりました。
——かなりの効率化と言えますね。
梅川:生産性が1.9倍になれば固定費が約2分の1になる。また、変動費のほとんどはエサ代で、それが4割減になる。
エサを減らせるだけでも先ほどのタンパク質不足や環境負荷の対策に貢献できますが、コストの低減によって陸上養殖でもしっかり事業採算性が取れるビジネスモデルを構築していくつもりです。
5年以内に東南アジアに進出したい
——すでにタイとトラフグをオンラインで販売していますが、今後の展開は?
梅川:現在、魚類10品種、エビやイカのような無脊椎動物10品種、計20品種の品種改良を同時に進めており、そのすべてを今後2〜3年で市場に出せるように準備しています。
——今後どのようにスケールさせていく計画ですか?
梅川:短期的には、我々がつくる品種を一緒につくってくださるようなパートナー、各地域の水産業に従事されている方々との協力を進めていくつもりです。
我々の陸上養殖「スマート養殖」は労働負荷も軽減できます。これまで“男性の産業”だった水産業を、さまざまな担い手を呼び込んでいきながら盛り上げていきたいと思っています。
——長期的にはどうですか?
梅川:グローバルな展開ですね。どうしても海外から買わざるを得ない品種もあるので、そうした品種もコストが安く国内でつくれるのであれば、大きなメリットになる。そのためにも、5年以内には東南アジアへ展開し、長期的に東南アジアでかなりのシェアを占める形に持っていきたいと思っています。