●メディア向けのインタビューも余すところなく掲載!
ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンが、2011年9月3日に開催した“『ICO』『ワンダと巨像』Great Scene Sharingキャンペーン プレミアムイベント”。これは、Graet Scene Sharingキャンペーン(以下、“GSS”)という、『ICO』、『ワンダと巨像』の2作品から思い出深いシーンを選び、TwitterやFacebook、mixiなどのソーシャルメディアに、そのシーンへの思い入れを投稿するキャンペーンの一環で行われたイベントだ。同イベントには、『ICO』と『ワンダと巨像』の生みの親・上田文人氏に加え、『SIREN』シリーズを手掛ける外山圭一郎氏が参加。プライベートでも仲がいいというおふたりらしく、熱く、そして深いトークをくり広げた。本記事では、先日お届けしたイベントの概要(【コチラの記事】)とは別に、イベント内であったおふたりのトークセッションと、おふたりを対象に行われたインタビューの模様をノーカットでお届けしよう。同イベントに参加できなかった人は、この記事でイベントの雰囲気を味わっていただければ幸いだ。『ICO』と『ワンダと巨像』の裏話満載のトーク。ぜひ余すところなく読んでいただきたい。
▲『ICO』、『ワンダと巨像』の開発者・上田文人氏。最新作は、プレイステーション3(以下、PS3)で発売予定の『人喰いの大鷲トリコ』。 |
▲『SIREN』シリーズの開発者・外山圭一郎氏。最新作は、PlayStation Vita(以下、PS Vita』で発売予定の『GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動』。 |
●トークセッション:『ICO』と『ワンダと巨像』の思い出
――まずは『ICO』の思い出についてお伺いしたいのですが?
上田文人氏(以下、上田) 僕が初めてゲームデザインとディレクションをしたんですが、当時はわからないことだらけで苦労した思い出の作品ですね。今回PS3になって解像度が上がり、テクスチャーや3D立体視への対応などをしていますが、自分がいちばん見てほしいと思っているもの、あの当時志したものはいまでも変わらずに評価されると思いますので、PS2版をプレイしたことがある方には懐かしみながら、楽しんでもらえればと思います。
外山圭一郎氏(以下、外山) 端的に聞きますが、HDになってここがいちばん変わったというのは?
上田 さっき言ったように解像度が上がったことを始め、細かい部分は変わっているんですが、ほかはあえてオリジナル版を忠実に再現してPS3に持ってきているんです。
外山 オリジナル版のさらにオリジナルで、じつはPS2の発売前に初代PSで開発をしていましたよね? そのころの映像を見る機会があったんですが、そこで驚いたのはいまと比べてシステムがまるで変わっていないところ。今回のPS3版の映像を見せていただいてもそれは同じで、本当にゲームが一貫しているんです。『ICO』が作られた10年前のゲームは、もっともっとアイテムが豊富で、長い時間遊べてというのが当たり前だったときで、よくその時代にこういうゲームを作ろうと思ったなって感じます。
 |
上田 これもいろいろなところで言っているんですが、もともと自分はゲーム業界に入ってはいたんですが、ゲームの根幹部分、いわゆるゲームデザインやディレクションをしていた人間じゃなかったんです。その後、ソニー・コンピュータエンタテインメント(以下、SCE)に移ってきて、ゲームを作れるというチャンスをもらったとき、……そのときから外山さんはゲーム制作の経験が豊富だったと思うんですが、そういった経験のある人たちにどういう商品価値がある作品で太刀打ちできるのだろうかと考えるわけです。結果、極力そういうゲームらしいものを排除していって、……自分が若かったというのもあると思うんですが、人がやっていることの逆をやろうと。『ICO』を作るときの最初の発想はそんな感じだったんですよ。
外山 日本のゲームとしては、見たことがないものでした。
上田 前に外山さんが言っていましたよね。外山さんとこうやって話したり、お酒を飲みに行ったりすることは、じつはけっこう最近のことなんです。それまでは同じフロアでゲームを作っていたんですが、外山さんが『ICO』がゲーム雑誌に紹介された当時を振り返って、「絶対に海外で作ってると思ってた」って言うくらいの関係だったんですよ。
外山 そうなんですよ。僕はSCEに移って最初はデザイナーとしてホラーとも違う『夜明けのマリコ』っていう作品に関わっていたんです。じつは『ICO』と同じ発売日で。
上田 2001年の12月6日ですね。
外山 だからファミ通で『ICO』の記事を見たときに、SCEで惹かれるゲームがあるけど、海外のスタジオの作品を持ってきたのかなって思ったくらいでした。
上田 そうしたら、まったく同じ社内で作っていたと(笑)。
外山 びっくりしました(笑)。
 |
――では、『ワンダと巨像』に関してはいかがでしょうか?
上田 『ICO』が終わって、『ワンダと巨像』を作ったきっかけというのは、『ICO』で長いあいだお城の中で細かい整合性を取ったギミック、レベルデザインと言うんですが、その作業を4年間くらいずーっとやっていたことが影響しているんです。パズルはおもしろいんですけどね。言葉は悪いんですが、ちまちましたパズルはもう作りたくないっていう思いが出まして。つぎはアクション活劇で、プレイしたとしても、偶然性の高いタイトルを作りたいというところから『ワンダと巨像』が始まったんです。じつは、もともとはオンライン対応のゲームだったんですが、それがいろいろ形が変わって、いまのスタンドアローンタイプのゲームになりました。。
外山 ちょうど僕が『SIREN2』を出しているころですね。僕が2本を出すあいだに、1本くらいのペースで(笑)。『ワンダと巨像』の発売少し前に、当時の上司と「『ワンダ』どうなんですかね?」って丁度話題にしていたんです。そうしたら、「ボス戦がすごいんだよ! でも、ボス戦しかできてないみたいなんだよね」って(笑)。それからどうするんだろうと思っていたら、ボス戦しかないゲームだった(笑)。
上田 当時、すごい決断をしたってよく言われました。ボス戦しかないデザインもそうですが、広大なオープンフィールドを作って、本来であれば敵を配置したりするはずが、敵がいないという(笑)。
外山 『ワンダと巨像』のようなゲームは、後にも先にもないなと思っています。あと、『ワンダと巨像』がすごいのは、その後のゲームへの影響力です。とくに海外のクリエイターさんに多く、『ゴッド・オブ・ウォー』などを作った方々などが「影響を受けた」と言っていますね。
上田 非常に光栄です。ただ、巨大な敵に限らず、そういうものにしがみついて、インタラクション(相互作用)するゲームは今後主流になると、自分では思っていたんですが、さほど主流にならなくて。主流にならないなら、じゃあ僕らで作りましょうという経緯で、『人喰いの大鷲トリコ』を作っています。
――外山さんは『ワンダと巨像』を最後までやられたんですか?
外山 もちろん(笑)。いまはHD版をやるのが楽しみです。本当は、今日のイベントのためにプレイしようかなと思ったんですが、PS3版の発売まで取っておくことにしました(笑)。
●トークセッション:GSSで選ばれたシーンの裏話
――GSSとして、たくさんのユーザーさんにお気に入りのシーンをお答えいただいていますが、外山さん、上田さんにもお答えいただいたので、そちらを発表させていただきます。まず外山さんの『ICO』のお気に入りシーンは、“シーン9 崩れる橋”ですね。
外山 僕が『ICO』をプレイして驚いたのは廃墟感なんです。
上田 廃墟、好きですもんね(笑)
外山 仕事柄(笑)。実際に取材で廃墟を見に行ったんですが、そういうところで肌で感じられる荒涼とした感じ、危険な感じ、生々しさが『ICO』の世界でもうまく表現されているのが、印象に残っていたんです。
上田 なんでこういうシーンを作ったかと言うと、橋が崩れてヨルダが宙ぶらりんになることで、“この先でも手をつないでくださいね”っていう、メッセージを伝えるためだったんです。
外山 昔、よく上田さんに聞いたことがあって。「いろいろな廃墟の取材に行ってるんですよね?」と聞いたら、その答えが……。
上田 一切行ってないんです、と(笑)。
外山 かなり驚いたんですよ。そのときも「取材しないでこういう表現ができるものなんですか!?」と聞いたら、「できてるんですから、取材はいらないんです」という身も蓋もない言葉が(笑)。
上田 (笑)。取材に関しては、自分の中でいろいろな思いがありまして。でも、『ワンダと巨像』で言いますと、乗馬の取材だけ行ったんです。それは参考にしましたね。愛馬であるアグロのモーションや、乗ったときの感覚と言いますか。クルマのようにアクセルで自分で操作できるものは暴れたりすることはありませんが、馬はダイレクトに操作できないので、急に暴れて「おっと!」となる部分などが参考になって取り入れましたね。
外山 あと、このシーンですごいと感じるもう1点は、カメラの巧みさです。10年前のゲームはそこまでカメラにこだわっていたわけじゃないんです。でも『ICO』は広角、望遠で高さ、広さを表現するのがかなりすごかったです。
上田 それまでのゲームでは、視認性や見やすさを重視していたんです。それに対して、『ICO』ではゲームを進行するうえでは、もう少しカメラが早く動いてくれればという部分があって。それでもリリースしたんですが、そこにはあまり不満が出なくて、「よかったよかった」と(笑)。
 |
――続いて、外山さんが選んだ『ワンダと巨像』のシーンは、“シーン20 最後の一撃は切ない”です。
外山 ここと言いますか、この後の一連の流れですね。巨像が倒れて、触手みたいなものがワンダに入ってくる、あそこまでの流れ。ふつうゲームでいちばん褒めてくれる場面で、すごくイヤな気持ちというか、背徳感みたいなものを感じさせられる。
上田 そこには裏話がありまして。もともとゲームを作るときって、最初から楽曲ができているわけじゃないので、巨像を倒す場面で仮の曲として、とある映画のサントラの物悲しい音楽ををこっそり入れていたんです。そうしたら、その場面をプレイしたスタッフが爆笑して(笑)。本来ファンファーレが鳴るような場面で悲しい曲が流れるので、何かの間違いじゃないかって思ったわけです。それはすごく鮮明に覚えていて。多数決でモノを作るのもいいんですが、それには危険性もあるんだなって思いました。実際に『ワンダと巨像』がリリースされた後、ユーザーの皆さんがその場面に違和感を持ったかと言うと、そういうことはなく……。まさに思い出深いですね。
 |
――では、上田さんが選んだお気に入りのシーンに移ります。『ICO』では、“シーン23 その手を放さない”。
上田 これはゲームデザインの細かい話になっちゃうんですが、ここではイコ(プレイヤー)に対して、“ジャンプしよう”なんてことは一切言わないシーンなんです。ここまでヨルダと旅をしてきて、こういう状況に置かれたときに、「ここでどうするか?」とプレイヤーに委ねたシーンなんですね。「みんながみんなジャンプをしてくれるんだろうか?」と思っていたんですが、いざ発売された後のレビューなどを見ていると、「僕はジャンプをしました」という意見が多くて。ここはレベルデザインとして大成功したなと思いました。でも、ここは本当に苦労しましたね。まわりの環境を作って、いかにそのように感情移入してもらうかというシーンなので、それで大成功したので、おかげで記憶に残っています。
 |
――続いて『ワンダと巨像』は、“シーン34 崩れる橋”ですね。
上田 これはエンディングの一部のシーンですが、僕が気に入っていたのはエンディング全体なんですね。なぜ記憶に残っているかというと、『ワンダと巨像』は大谷幸さんという方に作曲していただいたんですが、たくさんの曲がある中で、「ここでこのフレーズを使おう」といったシーンごとの曲を全部自分で編集して、それでサウンドスタッフに依頼をしたんです。一部の曲は変わっているんですけど、それが自分で何回聴いても、「この音楽の使いかたはいい」と自信を持っていたので、ここが気に入っています。
外山 『ICO』も橋じゃないですか(笑)。上田さんの中で崩れの美学とか、原体験があるんでしょうか?
上田 いえ、そういうことはなく、ゲームの整合性から考えると扱いやすいシチュエーションというのがあるんだと思います。……でも、もしかしたら自分の原体験で橋というのがイメージとしてあるのかもしれませんね。
外山 当時聞いて驚いたのが、物体が崩れる動きはたいていCG上の物理計算でやるんですが、ここの動きはすべて手で付けたと。
上田 はい。でも、この当時は物理計算自体をゲーム機の中でリアルタイムに動かすことは到底不可能でしたし、それを計算するための3Dツールの安定性も当時はよくなくて。これくらい大きな岩が落ちる動きは手で付けるしかなかったんです。
外山 試したけどよくなかったとかじゃなく、それしかなかった?
上田 そうですね。あと、じつはここまで崩すつもりはなくて。とくに『ICO』はもっとこじんまりした物語で終わらせようと思っていたんだけど、どうしても収まりが悪くて。「じゃあ崩壊だ」って(笑)。
――ユーザーの方々にもGSSキャンペーンに参加していただいていますが、ここでご参加していただいている方々の中で、「このシーンが好き!」というのはありますか?
お客さん 『ICO』の“NO.9 崩れる橋”なんですが、あのシーンでヨルダの手を放していたら落ちてしまったかと思うとゾッして。その後はずっと手をつないでいました。
上田 まさに狙った通りです(笑)。
お客さん 『ワンダと巨像』で、ワンダがモノ(ワンダが蘇らせようとしている女性)に近付いて、彼女の頬に触れるシーンが印象的でした。
上田 ワンダとモノが触れ合うシーンは本当にないんですよね。そのシーンは、せめてあれくらいでもと思って入れたカットなんです。あのくらいが表現としてはギリギリかな(笑)。
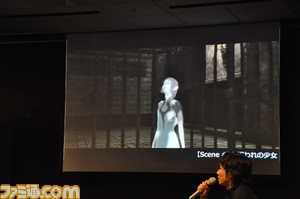 |
――2011年9月1日時点のGSSで、『ICO』の中でもっとも投稿されているのは、“シーン3 囚われの少女”です。このシーンで気を付けたところはありますか?
上田 イコとヨルダが出会うシーンですが、お互い知らないキャラクターどうしで、ここで初めて対面する場面でしたので、そのふたりの距離感をうまく表現できないかなと考えていました。引いたカメラで右にイコ、左にヨルダがいて、駆け寄るわけではなく、一歩一歩近づいていくシーンなんですね。あえて引いた状態で傍観者的な立場で何かをしているというのを意識しました。
――ヨルダのイメージを崩さないようにといった点はありましたか?
上田 それはめちゃくちゃありましたね(笑)。ゲームのこのシーンに限らずですが、映像を公開するときに、「この顔のこのアングルはやめてください」といったお願いをしたことが、けっこうありました。
 |
――GSSで『ICO』で2番目に投稿されているのが、“No.9 崩れる橋”でした。そして『ワンダと巨像』でもっとも投稿されているのは、外山さんと同じく“シーン20 最後の一撃は切ない”で、2番目に投稿されているのが、“シーン16 友とともに大地を揺るがす”です。こちらの場面は?
上田 アグロですね。実際にプレイされた方の意見を見ると、本当にこの馬に対して、思い入れを強く持たれている方が多くて。自分が作っているときは、そこまで思い入れを持ってくれるキャラクターになると思っていなかったんです。たとえば、このシーンで言うと、アグロがいないと勝てないシーンなんですが、そういう巨像が多くいるのかというと、それほどいない。そういう状況で、コミュニケーションらしいコミュニケーションはありませんが、遊んでいるプレイヤーは、いっしょに冒険をしながら、自分の中でイマジネーションを強くしてこの馬を愛してくれたんじゃないかなって思いますね。
外山 上田さんはバイクがお好きですよね。『ワンダと巨像』の中の馬との距離感は、ちょっとそれに共通するものがあるのかなって思うんですが?
上田 オートバイも、動物も好きで。そういうところはあるかもしれませんね。僕が思っていたのは、アグロという馬は、ワンダが飼っているペットとか友だちではなく、相棒であり、誤解を恐れずに言えば、道具、足ですよね。それぐらいの上下関係がしっかりしている動物なんだという関係を見せたかったというのはありますね。
外山 完全なコントロールができず、意思疎通が成立しえないものとの絶妙な通じかた、うまく通じていると感じられることが、『人喰いの大鷲トリコ』でも受け継がれているテーマなのかなと思いました。
上田 まさにそうですね。この『ワンダと巨像』でアグロとの関係性が、自分の想像以上にプレイヤーの思い出に残ったというのを聞いて、その部分はもう少し注力して表現できるものがあるんじゃないかと思ったんです。それが、『人喰いの大鷲トリコ』の企画がスタートした理由のひとつですね。
●トークセッション:作品を創作するにあたって
 |
――おふたりがせっかくお揃いですので、よりクリエイティブなお話を伺えればと思います。作品を創作するにあたって、おふたりのこだわりは?
外山 こういう話は散々飲みながらやっているんですが、なかなか皆さんにお聞きいただく機会はないので。上田さんは世界観が鮮烈だから、そこを重視して、世界観を再現するために作るという工程だと思われがちなんです。でも、話してみるともっとメカニックなところから入るという意外なところがありますよね。
上田 設定ありきで作ったことはないんですよね。でも、強烈なビジュアルイメージが浮かぶことはあります。『ICO』だと、自分より背の高い女の子と手をつないでいる男の子というのがビジュアルインパクトとして強いだろうと。『ワンダと巨像』だと馬に乗って草原で佇んでいたらかっこいいなっていうのがあるんです。でも、それと同時にメカニックも考えていて、『ICO』だと手を引っ張るとか、『ワンダ』だと馬に乗って巨大なものと戦って、巨大なものによじ上るというところ。まずはそこが重要で、それはどんな世界なのかとか、どんな衣装を着ているかとか、どれくらいの広さだというのは、外山さんがおっしゃったように、ゲームデザインの機能性や整合性から考えていって、その中で選択できるベストのものを選んでいくんです。
外山 先ほども、「最後は崩壊するつもりはなかった」と話していましたが、それは作ったうえでの必然性というものですよね。決して、その順序は逆にならないと。上田さんはもともとメディアアートをやられていて、それがテクノロジーと表現という根っこの部分になりますよね。
上田 外山さんは僕と同い年ですから。昔のビデオゲームというのは、ビデオゲーム=テクノロジーの進化みたいな部分がありましたよね。ですから、僕らの世代はテクノロジーから大きく外れて考えにくいというか、テクノロジーに対してロマンがある最後の世代なんじゃないかなと思うんです。いい意味でも悪い意味でも、そこからは逃げられない。外山さんのイメージの作りかた、創作性はどうなんですか?
外山 近いところはありますね。ビジュアルイメージはストックとして自然と溜まっていることがあって。あるところで、ギミックと結びついてゲームの原型になる。最初に上田さんとお会いしたころに話して印象深かったことがあって。僕は昔、『サイレントヒル』を作っていて、あのゲームは周囲しかライトで照らせないんですが、「あれが独特の世界観を出している」と言われてうれしかったんです。でも、あれは最初からそうしようとしていたんじゃなくて、PSの性能でフルポリゴンでリアルな世界を描くと、近景しか描けない。じゃあ、遠くは真っ暗にしてしまえという流れだったんですが、その話をしていたときに、『ICO』の世界観の話になったんです。
上田 そうですね。『ICO』も遠くまで描けないので、じゃあ周囲を海にしてしまえ、そして霧を濃くしてしまえば、ディティールを見せる必要がないねって考えかたで作ったんです。いまある技術や表現をどう使えば、最大限説得力のある絵やゲームになるかという考えかたは近いかもしれませんね。
外山 AI駆動も当時は重たいものなので、たくさんの敵キャラ、仲間がAIで動いているのではなく、ひとりのパートナーに絞っている。そこがおもしろいですね。
上田 それは一点豪華主義で。スタッフが少なかったというのもあって、ここに賭けるんだっていうのは、『ICO』ではヨルダで、『ワンダと巨像』で言えば変形コリジョンを使ったところなんです。『サイレントヒル』で思い出しましたが、『サイレントヒル』がリリースされたころに、ちょうど『ICO』を作っていたんですよ。それで『ICO』の音楽はあまりゲームっぽくない、ポピュラーミュージックにしたいってずっと思っていたんですが、なかなかそれを伝える手段がなかったんですね。その状態で、『サイレントヒル』のオープニングを聞いて、「まさにこんな感じ!」と。『サイレントヒル』だけじゃないんですけど、それをサンプルにして、こういう風にしたいって話をしたんです。
外山 当時、スタッフに山岡晃(『サイレントヒル』シリーズのサウンドやプロデュースを担当。現グラスホッパー・マニファクチュア所属)がいた幸運があったんですが、僕はかなり若くしてディレクターをやることになったので、せっかくなら同じことをやらず、ゲームでやっていないことをやろうって思ったんです。
上田 そういうところは僕も近いですね。自分のものを作りたいという作家性の部分と、ビジネス的に成立させないといけない部分。それは組織の中でものを作るうえで必要なことなんですけど、そのバランス感覚が近いんじゃないかなって思います。自分のものを作りたいというだけの人もいるし、「ビジネス、ビジネス」と言う人もいるし。それは両極端で、うまくミックスできればいいんじゃないかな。
外山 僕らは世代的に恵まれたというか、ゲームのハードが飛躍的に進化して、いままでやっていない裾野がバッと広がった。まわりを見渡せばブルーオーシャンという状態でしたから、何かをやったら新しいと思ってもらえるという。そういった意味で、いまはなかなかきびしいですね。
●トークセッション:今後の活動について
――では、今後の活動をおふたりにお伺いしたいのですが?
 |
上田 今後は、『人喰いの大鷲トリコ』というタイトルをなんとか満足のいく形で完成させなければいけないと思っています。というのは、僕の信念として、娯楽商品である限りは、実際に優れているかどうかは別にして、お客さんにとって、ゲームプレイヤーにとって、ほかよりも優れたものであると感じてもらわないといけないと思っているんです。どうしても仕事としてやっていく中で、それがまっとうできることがあれば、できないこともあると思うんですが、僕のいまのディレクターや、ゲームデザイナーという立場であれば、できるだけそれをまっとうできるように今後も抗っていきたいなと思います。
 |
――では外山さんは?
外山 年末に向けてPS Vitaという新しいハードが出ますので、その盛り上げに貢献するべく『GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動』というタイトルを鋭意制作中です。せっかくなので映像をご覧いただこうかと思います。(『GRAVITY DAZE』の映像が流れる)もともとホラーゲームをやる前からこういうゲームを作りたいなと思っていて、それがやっと手掛けられるということで、すごく気合が入っています。東京ゲームショウ2011で実際に触れる形で出展しますので、ぜひ東京ゲームショウ2011に遊びに来てください。
上田 僕もこのタイトルはずいぶん前に触らせてもらったことがあるんです。最近社内で、「すごくよくなってる」、「いい感じになってきてる」と聞いていますので、またこっそり遊ばせてください(笑)。
外山 けっこう苦労が長かったんですが、なんとか追い風を感じているところです。PS Vitaともどもよろしくお願いします。
――では、最後に上田さんから皆様にひと言お願いします。
上田 2011年9月22日に『ICO』、『ワンダと巨像』のPS3版が発売されるんですが、このような形で、かれこれ10年前、6年前のタイトルがリリースできるようになったのは、日本だけではないでしょうが、ファンの方が応援してくださった結果じゃないかなと思います。それはとても光栄なことなんですが、ただ気持ちとしては、いま自分がやっている『人喰いの大鷲トリコ』という最新作が代表作になるようにと思っているので、今後ともよければ応援してください。よろしくお願いします。
●トークセッションを終えて
 |
ここからは、トークセッション後に行われたメディア向けのインタビューの内容をお届けする。トークセッションでは聞けなかった、おふたりならではのインタビューを堪能していただきたい。
――本日のイベントの感想をお聞かせください。
上田 思ったよりも楽しいイベントでした。相手が外山さんで、ふだんからよくゲームの話をしていることもあって、あまり緊張することなくできたかなと。
外山 本当に緊張していたんですが、ちゃんと盛り上げられたかな。終わってみると、もっともっと話し足りないくらいで。非常に楽しかったです。
――『ICO』と『ワンダと巨像』はどちらもヒットした作品ですが、直接的な続編を出されていません。今回もHDになっていますが、システムはいじっていないというのは、一度作った作品に手を加えたくないという考えなのでしょうか?
上田 そうですね。『ワンダと巨像』は、すでに2005年にリリースしているタイトルです。当然「巨像を増やしましょう」といったアイデアがなかったことはないんですが、それをやってしまって「あのときオリジナル版は完成していなかったの?」と思われるのは野暮ですし、いまの最優先事項は『人喰いの大鷲トリコ』ですので、あまり時間がかけられなかったんですね。そのふたつの理由があります。
――おそらくこういったファンの方を前にして、しゃべるということは初めての経験だと思いますが、ファンの方の声を聞いた感想はいかがでしたか?
上田 最初は本当に来てくれるのかなって思ったんです(笑)。実際に会場に来られた方を見て……。
外山 真剣そのものでしたよね。
上田 そうですね。いまリリースされたタイトルではなく、ずいぶん前にリリースされたタイトルですが、作っているときから、できるだけ長く、消費されずに愛されるタイトルにしたいという気持ちを思っていたタイトルでしたので、実際に来られたお客さんを見ると、それはある程度成功したのかなと思えて、うれしいですね。
――おふたりのゲームの好きなところはどこですか?
上田 作るゲームが好きと言うのもあるんですが、ゲームデザイナーとして共感する部分が多いですね。たとえば『SIREN』で言うと、メカニックとして視界ジャックというアイデアがあって、それをベースにゲームを組み立てていくときにどうしても難易度が上がってしまう。そこでどうするかと考えたときに、僕も同じように難易度は下げたくないって思いますし、そこは変えちゃいけないんだろうなってときに、きっちり変えていないところは、シンパシーを感じますね。
外山 僕のほうで言うと、上田さんの作品のとくに人間性のところです。
上田 本能的なところですか?
外山 そうですね。ゲームのルールの表現ということではなく、実際にゲームに触れたときの気持ちの変化とか、そういったところをすごく掘り下げているのが、ほかでは見られないので、非常に稀有な作り手だなと思います。
――『ICO』と『ワンダと巨像』の解像度が上がったことで、できるようになった表現というのはありますか?
上田 解像度が上がったことでできることになった表現というのはありません。ですが、もともとPS2で作っていた両作品は、画面に表示できないくらいの情報量を詰め込んでいたんですね。たとえば指の動きとか。当時は「そんなことやって無駄じゃないか」と思われていたかもしれませんが、今回HDになってそういうところまで視認できるようになった。それはこれまでプレイしてきた方にも新たな発見になるんじゃないかと思います。
外山 3D立体視への対応はまったく新しいところですよね。
上田 そうですね。3Dはいろいろ調整をしたんです。両タイトルとも3D向きで、とくに『ワンダと巨像』は3Dに適したタイトルなので、ソニーのヘッドマウントディスプレイで遊んでほしいですね(笑)。
――映画でも3Dが主流になっていますが、その影響は受けていますか?
上田 正直に言いますと、いまの3Dよりは、昔の『キャプテンEO』などの飛び出す3Dのほうが、……自分が幼かったということもあるんでしょうけど、インパクトとしては大きかったですね。最近のはもっと落ち着いた3Dですから。
――これまでに影響を受けた映画作品を教えてください。
上田 たくさんありすぎてこれっていうのが……。このタイトルと1本だけを選ぶのはなかなか難しいんですが、ビジネス的にも成功していて、一般大衆の人たちも好んで観るし、玄人映画批評家などの玄人にもきちんと評価される映画というのは、ジャンル問わず好きですね。例を挙げると『ダークナイト』などですね。
外山 同様にこれっていうのは難しいんですが、自分が子供のころに受けた影響は大きいのかなって気がしています。
上田 ホラーとか?
外山 ホラーはまさにそうですね。テレビのCMとか、昔はトラウマ上等ですごいのがあったので(笑)。今回の『GRAVITY DAZE』という作品に関しては、学生のころからメビウス(フランスのマンガ家)の作品を目にしてすごくショックを受けていたので、いつかはこういう鮮やかな世界観をやってみたいと思っていて、それがやっと実現できたのでうれしいですね。
 |
――先ほど、おふたりはクリエイターとして似た部分がたくさんあるというお話がありましたが、逆にここが違うという部分はありますか?
上田 えーと、何か思い当たるところはありますか?
外山 僕はありますよ(笑)。
上田 どこでしょう?(笑)
外山 上田さんの肝の座り方がすごい。けっこう僕は作っているあいだに、チーム内から「こうしたほうがいい」とか、「もっとこうだ」とか言われると揺れるタイプではあるんですが、上田さんは絶対にブレない。
上田 そうですね(笑)。でも、外山さんも昔はそうだったんじゃないですか? 変わってきてるということではなく?
外山 僕は、コンセプトが維持される限りは、見た目とか手法が思いも寄らないほうに行ってもかまわない。
上田 そういう意味では僕は自分が作っている隅々まで行き渡らせたいというところが、いまはまだ強いかもしれないですね。それでも、以前に比べたらだいぶ弱くなってきたんですが。
外山 最近でもまだデータを直接いじることがあるんですか?
上田 ここ数ヵ月はそうでもないですね。
――それは、自分でわかる状態にしておきたいということでしょうか?
上田 わかる状態にしておくのは当然として、どうしても何かを表現したいと思ったときに、もっといい表現が僕ならできる、もしくは誰かができるということであれば、その選択を取りたくて取りたくてしょうがなくなるってところはあると思います。
――『ICO』、『ワンダと巨像』がHD化されて、当時見たものと感覚が違うと悩んだことはありましたか?
上田 表現自体はさほどなかったですね。ただ、解像度が上がったことで本来きちんと表現されていなかったことがバレてしまって、それをいくつか直さなければいけないところはありました。
外山 真っ直ぐすぎるところが気になったりしませんか? 昔だったら、解像度が足りなくていい具合に揺らいでいたのが、くっきり表示されてしまうとか。
上田 ちょっとはあったかもしれませんが、それを改変していくと『トリコ』の作業に支障をきたしてしまうので(笑)。
外山 思ったほどではなかった?
上田 そうですね。とくに『ワンダと巨像』はビックリするほどHDにしても耐えられると思いましたね。さすがに『ICO』は初めて作った作品だったので、いろいろなところで技術的に足りてない部分あって修正項目が多かったんですが、『ワンダ』に関して言うと、それほどはなかったですね。
――3Dの話題が出ましたが、3Dだからこそ、ここを見てほしいというシーンはありますか?
上田 『ワンダと巨像』は2ヵ所あります。『ワンダと巨像』に関して言えば、馬で草原を走っているところで奥行きが感じられます。じつは地面が流れる演出があるんですが、2Dだと地面が流れているのがわからないんですね。それを3Dで見ることで奥行きがありつつスピード感があって。あと、たまに馬が石ころを飛ばしたりするんですが、それがいい感じに手前に飛んでくるんです。もうひとつは巨像戦で、何かを見上げたときの臨場感が上がるはずです。『ICO』で言うと、ステージのいくつかで見下ろして高さを煽るようなシーンがあるんです。ああいうところは効果的ですね。
――発売予定の作品について、上田さんは外山さんの『GRAVITY DAZE』を、外山さんは上田さんの『トリコ』についてコメントをお願いできますか?
上田 『トリコ』はコメントが難しいかもしれませんので(笑)、僕のほうから。『GRAVITY DAZE』は、僕はもともと外山さんがホラーじゃないものを作っているっていうことは以前から知っていたので、早く発表して意外性をアピールしてほしいなと思っていました。あと、ここ最近になってゲームの完成度が上がって、周囲のスタッフから「いい感じになっている」と伺っているので、早く触りたいなと思っています。
(C)2005-2011 Sony Computer Entertainment Inc.
※画面は開発中のものです。




