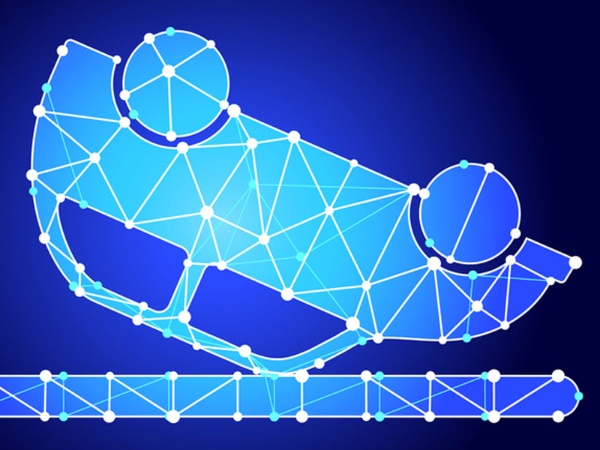開発されてきた駅前を森林に戻す──。千葉県のローカル線、小湊鐵道は、古い列車や駅舎を使い続けて、静かに人気を集めてきた。時代の流れに抗うかのような企業は、創業100年目を迎え、ついに「逆開発」に乗りだした。(下の動画をご覧ください)
今年3月、千葉県市原市の山間部にある観光の玄関口、養老渓谷駅。駅前のロータリーにショベルカーが入ると、工事関係者や鉄道職員が見つめる中、ついに歴史的な工事が始まった。


「逆開発」
駅前のアスファルトを、ショベルカーがうなりを上げながら剥がしていく。そして、土が姿を現すと、小湊鐵道の社員が土地をならし、木や花を植える。使い古した鉄道の枕木が運び込まれ、土に埋め込んで散策の道が作られていった。さらに、枕木を積み上げた「ウッドベンチ」も設置される。
「靴が汚れるじゃないか」「せっかく舗装した道を、なぜカネをかけて壊すんだ」
当初は批判の声も漏れてきた。駅舎の前にあったバス停は、離れた街道沿いに移設することになった。利便性を犠牲にする逆開発は、サービス低下に結びつき、人が遠ざかるのではないか、と。
だが、小湊鐵道社長の石川晋平は、利便性ばかりを追及した開発が、土地の持っていた魅力を覆い隠してしまったと見ている。
渓谷を駅前に進出させる
戦後、駅周辺の渓谷や滝、温泉といった観光資源が脚光を浴び、開発が進められてきた。1928年に「朝生原駅」として開業していたが、戦後の54年に「養老渓谷」と駅名を変えると、開発は加速度を増していった。高度成長にも乗って、温泉旅館や飲食店、土産物屋が立ち並び、駅前は舗装されてバスやタクシーが乗り付けるようになる。
だが、経済成長の終わりとともに、観光地としての勢いを失っていった。1日平均の乗客数は減少の一途をたどり、最盛期の半分近くまで落ち込んだ。商店街も櫛の歯が抜けるように閉店していった。そして、バブル崩壊で老舗旅館が相次いで破綻すると、駅前から人影がめっきり減って、アスファルトとコンクリートの殺伐とした風景が残った。
しかし、駅周辺のロータリーや駐車場を抜けていくと、わずか5分も歩けば、豊かな自然が姿を現す。駐車場を抜けて駅舎の反対側に向かうと、渓谷へと下る遊歩道があり、養老川に架かる橋へとつながっていく。絶景スポットだが、観光客は見当たらない。駅と自然との間を、アスファルトが遮断している形になっている。
「それなら、養老渓谷が駅前に進出した方がいい」(石川)
だから、アスファルトを撤去した後には、周囲の自然環境に存在する木や花を植えていく。違う種類の植物を使えば、人工庭園のような風景になってしまうからだ。地域の自然を、そのまま駅舎までつなげてくる。
そのため、会社が所有する駅前の土地約2000平方メートルを、アスファルトから土に戻していく。4〜5年で植林の作業を終え、10年後には木々が成長して、森林が駅を覆うことになる。
長い期間をかけて、自然の風景を取り戻すために、少なからぬ資金を投入する。1年目こそ、事業費2100万円のうち、地方創成の交付金で1500万円が補助される。だが、2年目以降は小湊鐵道がすべて負担する予定だ。年300万〜500万円の整備費を投じていくことになる。
「会社のカネで森を作るとは何ごとか」。そうした声を、石川はさして気にかける様子もない。なぜなら、森が再生することは、地域だけでなく、企業経営にとっても有益だと考えるからだ。
自然を使い倒す
「地域と会社の間に境目を作らなければ、自然の持つエネルギーがバランスシートの資産になってくる。悪く言えば、自然を使い倒す。これは理にかなった事業活動だと思う」
4月下旬。逆開発が始まって1カ月なのに、すでに木々が成長を始めていた。まだ、全体計画から見れば、ほんの一部しか手がつけられていないが、駅前の風景は大きく変わった。鉄道でやってくる若者や家族連ればかりでなく、クルマで通りかかった人々も、様変わりした駅前に集まってくる。枕木で作られたベンチに腰掛け、緩やかに流れる時間を過ごしていた。


石川は駅舎の前に石碑を建てた。「逆開発」という大きな文字に続いて、こう宣言する。
「10年後、ここ養老渓谷駅前は雑木が茂る森になります」
もう後戻りはしない──。石川が逆開発にこだわるのは、その先に「企業の未来」を見据えているからだ。
小湊鐵道は全長39kmのローカル線で、市原市の工業地帯や市街地を走る黒字の区間がある一方で、養老渓谷駅を代表とする山間部は赤字が続いている。それを市街地の黒字やバス事業の収益で埋めている格好だ。
はたから見ると、山間部を維持することが重荷に見える。だが、その地域は、都心にはない経済循環を生み出しつつある。山間部は、ほとんどが無人駅となっていて、駅と地域との境界が分からないほど風景に溶け込んでいる。そして、地元住民がボランティアで駅を清掃し、イルミネーションなどの装飾もして「集客戦略」まで担っている。
「鉄道を一体として捉えている。山間部を残すことこそ、会社の使命」。そう言う石川は、山間部に企業の価値やポテンシャルが潜んでいると見ている。
その考え方は、石川の2代前の社長だった祖父・信太の経営に寄るところが大きい。信太は1980年から28年にわたって社長、会長を務めた一方で、画家としても知られる。2000点を超える絵画を遺したが、その多くは里山の風景だった。
「それは開発じゃない、破壊だ」
「私は、失われる運命にあるものを現存する時にキャンバスに残したい思いに駆られて、スケッチに出かけるのかも知れない」(『石川信太自伝』)
そして、「絵を描くことと、会社の経営とは、その考え方に、共通するところがある」とも綴っている。信太はスケッチ旅行に出かけ、風景を前にして、指で正方形を作りながら、どう区切り、解釈して一枚のキャンバスに納めて作品にするか思案した。それは、意見やデータ、将来予測を鑑みて決断する会社経営に通じるという。
だから、信太は小さな駅舎を建て替えることもせず、窓枠をサッシにすることも許さなかった。列車も40〜50年前のものを使い続けている。
石川は、そうした祖父の経営哲学を、初めは理解できなかった。大学卒業後に千葉銀行に勤務していた時のこと。祖父と食事をしていると、こう聞かれた。
「お前、どういう仕事をやっているんだ」
家の中でも威厳を放つ祖父は、気安く口をきけない相手だった。ここぞとばかりに、銀行で再開発事業を手がけていることを話した。すると、思いがけない言葉が飛んできた。
「君がやっていることは破壊だよ。開発じゃねえよ」
返す言葉がなく沈黙した。祖父の深意は分からなかった。「開発と破壊」。その言葉だけが脳裏に刻まれた。
邪魔なものを省いていく
2008年に会長だった祖父が96歳で亡くなった。その翌年、入れ替わるように石川は社長に就くことになる。
「私なんか、何か言える立場ではありませんからね。ただ、じいさんが社長でいたから、こうやって(経営者を)やらせてもらっているだけですから。それなら、つないでいかないと」
そして、石川は「開発」の意味を考え抜くことになる。
養老渓谷駅に足湯を作り、飯給駅には市の協力によって「世界一、大きいトイレ」が設置された。だが、それで多くの人が集まるわけではなかった。飯給駅の1日の乗客は4人にとどまる。何かが足りない。
その解に近づいたのは、2年前のことだった。
「里山トロッコ列車」の運行を2015年秋に開始する。車両は窓を取り払い、天井もガラス張りの開放型にした。時速25キロでゆっくりと走るため、ほどよい風を受けながら、自然の風景を抜けていく。住民とも目線が合い、互いに手を振り合う。
「60キロで走ると見えないものがある。遮るものを省いていけば、そこにあるものが伝わるんじゃないか」(石川)
その後、夜にビールサーバーと地元産の弁当を積み込んだ「夜トロッコ」を走らせるようになった。地元の人々も乗り込み、遠方からやってくる人々との交流の場にもなっている。
列車内で人々が盛り上がる様子を見ながら、石川は呟いた。
「もしかしたら、これをやるためにトロッコを作ったのかもしれない」

トロッコは、地域社会と来訪者との距離を一気に縮めた。そして、思わぬ効果をもたらすことになっていく。
地元のボランティア団体連合会会長の松本靖彦は、トロッコから見える地元の風景に顔をしかめた。
「ちゃんと整備しないと、我々の地域のことが伝わらないと思ってさ」
山間部の月崎駅と上総大久保駅の間に、荒れたまま茂る竹林があった。そのすぐ横を、観光客を乗せたトロッコ列車が通っていく。
昨年8月、地元住民と小湊鐵道の社員、そして市原市役所職員の総勢60人が集まった。そして、炎天下の中を4日間かけて、雑木を切り倒して整備した。その中に、木を担いで運び出す石川の姿もあった。
「造園業者でも請け負いたくない作業だよ。ムリにやらせたら、数千万円は取られる」(松本)
自らの潜在力を発見する
トロッコ列車が年間を通して稼働した昨年度、養老渓谷駅の乗客数は平均200人近くに上り、24年振りに増加へと転じた。しかも、前年の2倍近い数字となった。
住民と来訪者が、互いに作用しあいながら、地域が変わり始めている。逆開発は、その流れの延長線上にある。人々は駅を降りた瞬間に、豊かな自然を感じることになる。そして、人が増え、滞在時間が延びていく。
「開発という字は『かいほつ』という禅の言葉で、自分を気付かせることを言う」。養老渓谷駅に近い宝林寺住職の千葉公慈は、人と人が交錯することで、互いに自分の潜在力に気づくという。地域社会も、来訪者が来ることで、その地が秘めている能力や可能性を発見し、伸ばすことができる。
「だから、小湊鐵道は『逆開発』と言っているが、実は開発そのものなんです」

自分たちの良さはどこにあるのか──。少しずつ、来訪者と地域の間にある障害物を取り払い、ゆっくりと交錯する時間と空間を作ってきた。列車のスピードを半分以下に落とし、窓を取り払い、アスファルトを剥がしていく。
そして地域の潜在力を引き出す道が、はっきりと見え始めている。会社の未来も、その先に重なっている。
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。