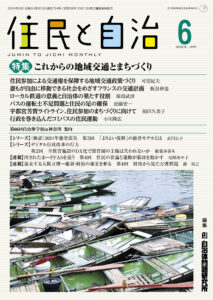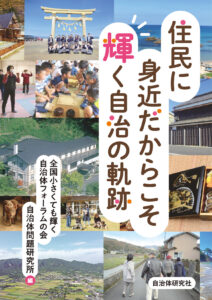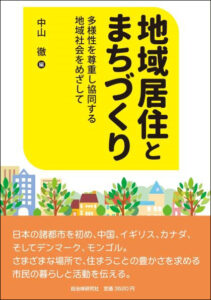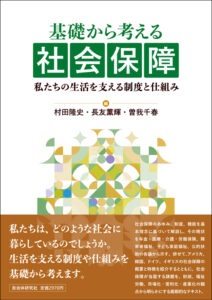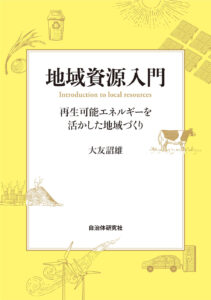人が育ち、生き生きと相互に関わり合うことができるような文化施設、住民が主体的に参加し、地域の魅力を発信していく地域文化創造の可能性が問われています。
はじめに
住民が相互に関わりながら共感し、生きる喜びを見いだし、創造性を発揮しつつ社会に参加するうえで、文化行政による公的な支援は不可欠です。少子高齢化、貧困・格差などの困難が増大している地域社会で、地域を元気にする自治体文化行政の役割とはどのようなものでしょうか。文化行政のあり方、文化施設の存在意義についてそれぞれの地域で考え、議論をおこしていくことが必要であると考えます。
戦後の文化行政は、文化財保護、芸術文化の振興、伝統芸能の保存などを中心に国レベルでは文部省(現文部科学省)社会教育局(現生涯学習局)が所管し、自治体レベルでは教育委員会に担当課がおかれてきました。1968年に文化庁が発足して、より自立的に文化に関する事項を所管するようになりました。1980年代以降毎年開催されている国民文化祭では、あらゆる分野の芸能・表現活動の全国的な交流・振興がはかられています。
他方で1970年代以降、「文化の時代」「地方の時代」の提唱のもとで地方自治体のレベルでは、首長部局を中心に独自の地域文化振興を模索する動きが生まれました。「行政の文化化」というとらえ方に表れているように、地域の景観や生活文化・福祉に着眼して、市民自治活動との連携による福祉文化的なまちづくりが追求されています。首長部局におかれた文化行政部局では、対象範囲を広げてまちづくりと結びついた文化芸術の振興から地域住民の暮らしを豊かにする生活文化にいたるまで幅広い課題をとりあげ、「文化ホールがまちをつくる」(森啓)といわれるような状況が生まれました。しかしその後の自治体財政の窮迫、文化予算の削減のなかで文化行政への関心は低下し、パラダイムシフトの必要性も指摘されています。
他方、2000年代に入り、国は文化芸術振興のための新たな法整備を進めています。2001年に文化芸術振興基本法(以下基本法)が制定され、国の文化政策の体系的推進のもとで地方公共団体が文化芸術振興条例や地域文化振興方針を策定し、公立文化施設の運営を活性化するよう方向づけています。
今号の特集では、自治体文化行政の推移を概観し、各地域の個性的な地域文化の振興や公立文化施設の運営の事例をとりあげながら、①自治体と住民が協働し、地域の文化的発展を生み出す過程で、それを支える自治体文化行政の役割とは何か、②一人ひとりが生き生きとした暮らしを営むうえで、公立文化施設はどのような役割を期待されているのか、その運営理念と課題、③主権者である国民の表現の自由や創造性を守りはぐくむ文化の公共空間はどうあるべきかなど、住民を主体とする地域の文化的発展の方向性を探り、文化行政と文化施設が直面する課題について考えてみたいと思います。
自治体文化行政の推移
国は戦前から、宗教、文化財、著作権、国語、芸術文化に関する事項を国の文化政策として推進し、特に軍国主義の時代には国家統制的な文化政策が推し進められました。このため、戦後は「文化政策」という用語自体もあまり用いられない状況が続きました。
戦後改革を通じて、平和で民主主義的な社会において国民一人一人が幸福を追求し、表現の自由を行使するという憲法13条、21条の規定、さらに「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(25条、生存権)が定められました。文化の享受と創造への参加は個々人の主権者としての選択であるとともに、国・地方公共団体が環境を整備する責任をもつ社会権的な権利であることが憲法に明記されています。これを受けて旧教育基本法は、「普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育」を基本方針にかかげました。
1949年に制定された社会教育法の第5条(市町村の教育委員会の事務)には「音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること」が定められています。公民館や博物館(美術館)などホールや展示場をもつ社会教育施設はもちろんですが、公立文化施設の約半数が教育委員会の所管とされていることも、この条項に根拠があります。
1950年に制定された文化財保護法では、「文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し」文化財を適切に保存することを政府及び地方公共団体の任務として定めています。(第3条)
このように戦後の法制度のもとで、文化財保護と芸術文化振興を地方教育委員会が所管する体制がつくられました。しかし1970年代以降の自治体文化行政の展開では、それぞれの地方自治体の判断によって、地域ごとに独自性をもつ文化行政を推進することを自治体の「革新」として追求し、大きな変化をもたらしたといえます。
当時、自治体文化行政論の提唱者として影響を与えた政治学者の松下圭一と神奈川県文化室主幹の森啓は共編著『文化行政 行政の自己革新』で、大量生産・消費、公害、地球規模での資源・エネルギー問題の深刻化を背景に、「〈地域特性〉をもつ生活の質の見直し」「自治・分権システムの構築」が必要であり、①市民自治の原則、②基礎自治体主導の原則、③行政の革新の原則にもとづく「市民自治」による「市民文化」の形成が中枢の課題であると提起しています。行政への依存体質を自己革新し、シビル・ミニマムにもとづく「地域空間計画」が求められていると提唱しました。
新しい文化行政論に共鳴する自治体を中心に全国文化行政連絡会議が発足し、1979年には第1回全国文化行政シンポジウムが開催されます。首長部局主導の文化行政が都道府県から中核的な自治体へと広がっていきました。
大きな旋風を生み出した自治体文化行政論の提唱でしたが、四半世紀を経てその原初の枠組みは矮小化されてしまったとの反省もなされています。たとえば上野征洋静岡文化芸術大学(当時)は、「1980年代に迎えた『地方の時代』の繚乱の中で、次第に『文化・芸術の振興』『文化会館の建設・運営』などへ傾斜してゆき(中略)、そこに『市民』のあるいは『地域社会』の顔はあまり見えない。(中略)『文化行政』には新しいパラダイムが必要である」と述べて、原点を検証しながら新たなステージに向かう必要性を提起しています。
文化芸術振興基本法の制定と地域文化振興ビジョン
国は、日本芸能実演家団体協議会(芸団協)を中心とする国際的な文化政策研究などと連携しながら、芸術文化の公的支援策の方向性を探り、芸術文化振興基金の設立、「アーツプラン21」などの支援策の推進を経て、2001年に基本法の制定へと文化政策を推し進めてきました。
基本法第2条(基本理念)第3項で、「文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない」と述べています。国法のレベルで初めて「文化芸術を創造し、享受する」文化権が明記されたことは画期的です。
この法律では「文化芸術の振興」の対象として、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術、メディア芸術、伝統芸能、芸能、生活文化、文化財、地域における文化芸術、国際交流などなどをあげており、きわめて包括的に「文化」をとらえています。
さらに文化芸術を「国民に身近なものにする」ために、その後国の文化審議会で2002年から2015年に4次にわたって「文化芸術の振興に関する基本方針」がだされました。その過程で2012年に「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」(以下劇場法)の制定、2013年に「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」(文部科学省告示)がだされました。文化芸術の振興、公立文化施設の芸術専用施設としての活用、そして地域文化の振興という課題について、国は体系的に法的整備を進め、文化振興ビジョンを提起しています。
一連の国の施策は、自治体文化行政の新たな展開を促しています。その一つは、地方公共団体は文化芸術の振興に関し、「自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」(基本法第4条)と規定したことです。これによって都道府県・市町村自治体の文化芸術振興条例の制定が促され、さらに文化芸術振興ビジョン、文化芸術振興計画の策定が方向付けられることになりました。
とはいえ、都道府県・政令指定都市はともかく、市町村全体ではまだ1割に満たない自治体が条例制定、計画策定を実現したにすぎないという状況にとどまっており、市町村自治体文化行政の新たな展開は容易ではないことがうかがえます。
公立文化施設の活性化
二つめに、国は劇場、音楽堂の施設を活性化して、地域文化振興の中心にすえていく方針を示しました。劇場、音楽堂とは、「人々の創造性を育み、人々が共に生きる絆を形成するための地域の文化拠点である」「人々の共感と参加を得ることにより『新しい広場』として、地域コミュニティの創造と再生を通じて、地域の発展を支える機能も期待されている」「国民の生活においていわば公共財ともいうべき存在」(劇場法前文)と述べています。公立文化施設が単に貸しホールとして機能するのではなく、演劇や音楽の上演、美術展示などを通じてなくてはならない存在、すなわち劇場、音楽堂として「公共性」をもつことが法律に示されています。
4次にわたる「文化芸術の振興に関する基本指針」では、文化芸術の「文化力」によって地域創生に寄与すること、生活の貧困化のなかで社会的に排除されている人々を「社会包摂」する機能、子どもや若者の参加と後継者の育成、学校や福祉施設などとの連携によるアウトリーチの展開などに言及し、劇場や音楽堂が地域社会のなかで住民や子どもたち、社会的弱者とみなされている人々と共にどのような文化芸術活動を創造しうるのか、ふみこんだ提言をしています。
1970年代当初に400館ほどしかなかった公立文化施設は、1990年代末には約3000館に達し、まさに建設ラッシュという状況でした。文化施設には数十億円という膨大な建設費とその後の維持費がかかりますので、当初から「ハコモノ批判」がありました。文化施設は文化芸術の普及・創造の拠点ですから、専門的な人材を集め、事業を行わなければ適切に運営することはできません。しかし地方財政悪化のもとでは人材と事業はもっとも大きな経費削減の対象となります。現在では、全国約3600館に及ぶ公立文化施設の多くは、人を減らしながら「ハコ」を維持するだけでせいいっぱいというジレンマをかかえています。
公立文化施設といっても設置目的、機能は多様です。「地域の公立文化施設実態調査」報告書では、公立文化施設とは「公の施設」で、「音楽、演劇、美術等の事業が行われている『ホール』、『美術館』、『練習場・創作工房』およびそれらを含む『複合施設』」とされています。3588館のうち56%が単独施設で、あとは複合施設等となっています。このうち市町村立は85・3%、3059館で、都道府県立、政令指定都市立がそれぞれ6・3%、8・4%です。
劇場法で「劇場、音楽堂」が明記されたことは画期的ですが、それまでこのような法的規定がなかったために、自治体が地域のニーズの中で施設運営のあり方を模索する状況が長く続いてきました。芸術監督を置いて非常に個性的で創造的に運用されている劇場や音楽堂もあれば、主に貸しホールとして使われる地方自治法による一般集会施設、主に住民が学習文化活動の発表の場として利用している公民館、博物館のような社会教育施設のホールなど、根拠法と設置目的という点でも多様性や異なる機能があります。劇場法は、このような公立文化施設の多様な実態に対して、一人ひとりの地域住民にとって公立文化施設がなくてはならない存在であり、心豊かな暮らしを支えるよりどころとなる可能性を問いかけているといえます。
公立文化施設の管理形態は直営が56・7%、指定管理(公募)が25・7%、指定管理(非公募)が16・8%となっています。専用ホールをもつ施設のスタッフは、都道府県・政令指定都市では10数人から20人以上が配置されていますが、施設の65%以上を占める人口20万人未満の自治体では、4人から8人程度です。とくに文化芸術領域の専門職員という点では人口20万人未満の自治体ではほとんど配置されていない状況にあります。都道府県施設の25%、政令指定都市施設の18%に専門職員がいるという実態からみると、市町村の場合、職員よりも外部の専門的な文化芸術団体・NPOなどに頼らなければ文化芸術を目的とした運営はなかなか実現できないということが実態として浮かび上がってきます。
さらに自治体の文化予算の問題があります。地方公共団体の文化予算は1993年度に9553億円に達しましたが、その後急減して2006年にはその4割以下の3000億円台となっています。なかでも文化施設の建設費が1993年には6000億円に近かったのが2000年代にはその5分の1程度となり、1館あたりの文化施設経費総額も1990年代半ばに8500万円であったものが2005年には5300万円台、事業費だけをみると2500万円から1100万円と5割以下に減少しています。2003年度の指定管理者制度の導入でとくに市町村の芸術文化経費の落ち込みが大きくなっています。
財政・運営態勢面での困難をかかえながら、公立文化施設として明確な存在意義を示すことがなければ、最低限の予算確保もできなくなっており、往年の「文化の時代」「地方の時代」とは大きく異なる自治体文化行政・公立文化施設の状況が示されています。
むすび
地域の文化的発展を支える自治体文化行政
自治体文化行政と文化施設のあり方は、2000年代の法整備を通じて新たな可能性をもちはじめていると同時に、困難やリスクをかかえていることを見落とすことができません。
第一には、利益を出せる事業、観客動員型のイベント、そのための民間資金誘導に傾斜しやすいということです。文化施設自体が観光の目玉になるという経営手法も重視されています。このために文化行政が観光と一体化する、あるいは観光客のための催しを志向する傾向もみられます。むろんそのことは地方創生が死活問題となっている地域にとって決して非難すべきことではありません。肝心なことは、そこでいかに地域住民自身の主体的な創造活動を発展させ、地域住民の総意と参加に支えられた地域の文化的発展の見通しを拓くかという点です。一過性、あるいは業者まかせではなく、地域の力量を高めていくために、持続的でねばり強いとりくみが重要です。
第二に、「教育はチャージ、文化はディスチャージ」として、かつてのように教育行政と文化行政を分立させる考え方を見直すべきです。地域の文化的発展を着実なものにするためには、そこで人が育つ、人々が育ち合うという人間的な成長の場としての文化施設、文化事業のあり方が求められます。社会教育施設や学校・保育園、障害者施設などでは日常的に人々が育ち合い、文化的な創造がおこなわれています。「劇場、音楽堂の事業の活性化のための取組に関する指針」で、教育機関、福祉施設、医療機関などとの連携を提唱している点は重要です。しかし分野を超えた連携、公と民の機関・団体の協力は簡単なことではありません。立場の違う施設や団体のていねいな対話と相互理解の積み重ねこそ連携・協力の土台となります。本号の事例からも多くの示唆が得られると思います。
第三に、文化施設の運営に際して行政主導の優先基準などを設けることに慎重であってほしいものです。行政や施設の主催・共催事業だけではなく、広く住民・多様な団体がみずから施設を使って創造的な表現を発信するために、施設が多様に活用されることが重要です。近年、政治的中立の観点から施設を貸さないという事件が多発しています。文化行政において市民主体の自由な表現活動を保障することがなによりも大切な原点です。あたかも行政が施設を所有し、行政が許可する、判断するという行政主導から脱皮し、住民主体、住民と行政との協働にもとづく施設運営の理念を真摯に追求するべきです。
自治体文化行政、あるいは文化施設が真に「公共性」をもつこと、すなわち住民にとってなくてはならない存在であり、住民と協働する主体となること、そのことこそが地域の
文化的発展を拓く鍵であると考えます。
【注】
- 1 森 啓『文化ホールがまちをつくる』学陽書房、1991年。
- 2 松下圭一・森 啓編著『文化行政 行政の自己革新』学陽書房、1981年。
- 3 日本文化行政研究会・これからの文化政策を考える会編『文化行政 はじまり・いま・みらい』水曜社、2001年。
- 4 文化庁「地方における文化行政の状況について」(平成26年度)2016年。
- 5 一般財団法人地域創造「平成26年度 地域の公立文化施設実態調査報告書」同、2015年。以下のデータもこの報告書による。
- 6 吉本光宏「再考、文化政策-拡大する役割と求められるパラダイムシフト」 『ニッセイ基礎研究所報』Vol. 51、2008年秋号。
- 7 佐藤一子『地域文化が若者を育てる』農山漁村文化協会、2016年、参照。