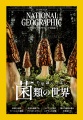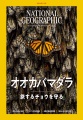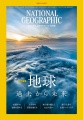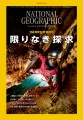「肉食恐竜としては最も大きかったものの、スピノサウルスは陸棲動物ではなかった」と指摘するのは、シカゴ大学の古生物学者ニザール・イブラヒム(Nizar Ibrahim)氏だ。同氏はナショナル ジオグラフィック協会が支援するエマージング探検家で、今回発表された論文の主著者でもある。「これは水中での生活に適応した生き物だった」。
スピノサウルスが登場するまで、恐竜が支配していた領域は陸上だけだった。それまでに1億5000万年にわたる進化を経た恐竜は、「スピノサウルスにおいて突如として生まれた適応により、泳げるようになった」と、同じくシカゴ大学の古生物学者で今回の論文の共著者でもあるポール・セレノ(Paul Sereno)氏は説明する。論文では、この恐ろしい肉食恐竜の生態を明らかにする、新たな化石の詳細が記述されている。
今回の論文で解説されている学名スピノサウルス・アエギュプティアクス(Spinosaurus aegyptiacus)の骨の化石は、モロッコ領内のサハラ砂漠にある砂岩層から発掘された。頭蓋骨、爪、さらには背中の帆を構成する骨がすべて揃ったこの化石からは、ワニを思わせる突き出た鼻面、オールのような足、浮力を増す効果を持つ骨密度の高さなどの特徴が見て取れる。これらはこの巨大肉食恐竜が水棲であったことを示す、さらなる証拠と言える。
◆第二次世界大戦の戦渦に巻き込まれた化石
1912年にエジプトの砂漠で最初にスピノサウルスの化石を発見したのは、ドイツの古生物学者エルンスト・フライヘア(男爵の意)・シュトロマー・フォン・ライヘンバッハだった。しかし、この時に発掘された化石標本は第2次世界大戦中のミュンヘン空襲によって破壊されてしまい、これがスピノサウルスに関する学術研究が停滞する原因となった。
さらなる化石標本の発見を目指したイブラヒム氏は、古い文献やドイツのバイエルン地方にある子孫が所有する城を調査し、シュトロマーの足跡を追った。この調査の過程でイブラヒム氏は、2009年にケムケム類層と呼ばれるサハラ砂漠の崖沿いで新たなスピノサウルスの化石を発掘した、ある化石コレクターの存在を知る。さらに同氏は2013年、これらの化石が見つかった場所を訪れてこのコレクターの居場所を突き止め、新たに発見された化石の出所と正確な年代を確認した。
◆骨格の再現
さらに今回、この化石を用いてスピノサウルスの骨格を再現したデジタル画像が作成された(これはナショナル ジオグラフィック協会の助成により実現した)。この画像では、鼻先から尻尾まで、半水棲の生態に適応した姿が明らかにされている。スピノサウルスの頭蓋骨には鼻先の中ほどに小さな鼻孔があり、これは現在のワニのようにアゴを水面下に沈めた状態で呼吸をするにはぴったりの構造だ。また、こちらもワニと同様に、鼻の先端部には神経と血管が通る穴が空いている。これにより逃げようとする獲物がもたらす水圧の変化を敏感に感知できたはずだ。
獲物の居所を突き止めた後は、スピノサウルスの後ろ側に傾いた円錐状の巨大な歯が、魚を捕まえるのに格好の武器となる。さらにはかぎ爪のついた、長く屈強な前腕で、歯では捕まえきれなかった獲物を仕留める。
長く伸びた首や胴も、これらの武器を活用するのに非常に適した作りだが、こうした特徴から、スピノサウルスは上半身が重すぎて陸上での二足歩行は不可能だったのではないかと推測される。後ろ脚は強力だが短く、その先端にある足はオールのように平らになっており、おそらくは水かきを備えていたと考えられる。これは泳ぎに適した構造だが、水から出ると機敏な動きは難しかったはずだ。
加えて、「脚の骨の密度が非常に高いことが判明し、これには我々も驚いた」と、イブラヒム氏は証言している。現在ではペンギンが同様に密度の高い骨を持ち、水中での浮力を確保するのに役立てているが、スピノサウルスの重い大腿骨も同様の機能を持っていたのかもしれない。
◆背中の巨大な「帆」の役割は?
また、スピノサウルスは背骨に沿って巨大な帆を備えているが、これが発達した理由も、水中生活に適した生態により説明できると、イブラヒム氏は見ている。背中にそそりたつ帆は、これまでに知られている恐竜の中では最も高さがあり、約1.8メートルにも達していた。
この帆については、専門家から熱を逃すための器官だとする説や、ラクダのこぶのように脂肪を蓄える役割を持っているという説が唱えられていた。しかし、今回の研究によると、帆の部分には熱を逃がせるほどの血管はなく、骨格は脂肪ではなく、「ぴったりとした皮膚」に覆われていたと考えられる。
おそらくこの帆は、ライバルへの警告や交尾相手への誘いなど、スピノサウルス科に属する他の個体に自らをアピールするものだったのではないかと、イブラヒム氏は推測している。帆は水面を泳いでいる動物からは目につくが、水面下にいる獲物からは見えないからだ。「目が水面より上にあるものにとっては、帆は非常に目立つ存在だったはずだ」と同氏は説明している。
今回の研究は、「Science」誌に9月11日付で掲載された。
Photograph by Mike Hettwer assisted by Mark Thiessen (NGM Staff)