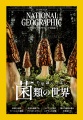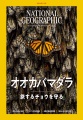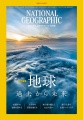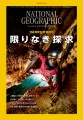古生物学者たちは長い間、恐竜は陸にすむものであり、水中に暮らすのは魚竜など爬虫類だと考えてきた。けれども近年の発見によって、陸上と水中の両方で生活した恐竜がいたという考える人が増えつつある。しかし、それをはっきり示す化石がないことが、研究者にとっての悩みだった。
このほど新たな手がかりが見つかった。6800万年以上前に生息した新種の恐竜が発見され、ペンギンやウなど潜水する鳥のように流線形の体をもっていたことが判明したのだ。鳥類と鳥類に最も近い恐竜以外で、この特徴が確認されたのは今回が初めて。研究成果は12月1日付けで学術誌「コミュニケーションズ・バイオロジー」に発表された。
モンゴル南部で発見されたこの恐竜化石は、ベロキラプトルなどを含むドロマエオサウルス類の一種。ラテン語とギリシャ語で「多く歯をもつ、泳ぐハンター」を意味する「ナトベナトル・ポリドントゥス(Natovenator polydontus)」と名付けられた。
多くの動物の肋骨は、背骨からほぼ90度の角度で出ているが、ペンギンやウなど潜水する鳥の肋骨は尾の方へ後ろ向きになっている。肋骨に角度がつくと、背中から腹にかけての幅が狭くなる。この体形は、水中を泳ぐときに役立つと考えられているが、科学者たちが観察したナトベナトルの化石には、まさにこのような適応が見られた。
現在の鳥には水辺で暮らすものが数多くおり、イクチオルニスやヘスペロルニスなど絶滅した鳥もそうだった。しかし、鳥類は恐竜の家系の一枝にすぎず、非鳥類型恐竜が湖や川に潜っていた証拠はほとんどない。ナトベナトルのように、泳ぐのに適した骨格をもつ恐竜が見つかったことは、恐竜の生息地や生活様式が、これまで考えられていた以上に多様であったことを意味する。
この点で、ナトベナトルは「恐竜の生態学的地位がいかに多様であったを教えてくれます」と、今回の論文の共著者で韓国ソウル大学の古生物学者、李隆濫(イ・ユンナム)氏は言う。
本当に水中を泳いだのか?
科学者たちはこの10年ほどの間に、少なくともスピノサウルス科の恐竜は、水と密接な関係をもっていたのではないかと考えるようになっている。スピノサウルスは、ほかの捕食恐竜に比べて明らかに水辺での行動が多く、解剖学的・化学的証拠から、少なくともときどきは海岸線をうろつき、魚をねらっていたようだ。(参考記事:「スピノサウルスの意外な尾を発見、実は泳ぎが得意だった」)
一部の研究者は、スピノサウルスの中でも最も大型のものは水中で過ごすことが多かったと主張しているが、反対意見も多く、つい最近も科学誌『eLife』に、スピノサウルスは泳いで魚を追いかけていたのではなく、浅瀬で魚を待ち伏せしていただけとする論文が掲載されている。(参考記事:「スピノサウルスの狩りは鳥のサギのようだった、新説」)
おすすめ関連書籍
大好評「NHKスペシャル 恐竜超世界」のシリーズ第2弾!日本にあった知られざる恐竜王国の姿を、躍動感があり、美しい豊富なビジュアルとともに、最新の研究から明らかにする。 〔全国学校図書館協議会選定図書〕
定価:2,200円(税込)