史記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/30 10:14 UTC 版)
後世の評価
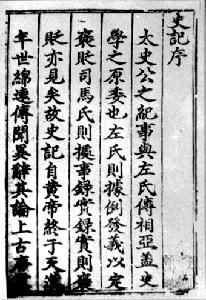
『漢書』との関係
後漢に編纂された班固の『漢書』は、『史記』の踏襲と批判の上に成り立っており、後世の『史記』評価の原点となった[33]。班彪・班固父子は、『史記』を以下の観点から批判している。
- 儒教の経・伝に拠りつつも、それ以外の学派に由来する内容を含んでおり、相互矛盾もある[34]。
- 黄老思想を儒教より優先し、儒教的価値観では批判されるはずの游俠・貨殖を称賛する[34]。
- 項羽・陳渉を押し上げて、淮南・衡山を退けたこと[34]。
- 司馬相如は本貫を郡県まで記し、字を記すのに、高祖の功臣である蕭何・曹参・陳平や、同時代人の董仲舒については、本貫の郡県や字を記さないといった不統一がある[34]。
これ以後、『史記』と『漢書』はよく対比されながら論じられることになり、後世の評価に大きな影響を与えた[33]。例えば、蜀漢の譙周は、「史書の編纂は経書にのみ依拠すべきであるのに、『史記』は諸子百家の説を用いた」と非難すると、『古史考』25篇を著し、経典の所説を遵奉して、『史記』の誤謬を正すものとした。劉勰の『文心雕龍』では、女性を本紀に立てたことが非難されている。
三国時代には、『史記』と『漢書』は「史漢」と併称されるようになり、これに『東観漢記』を加えて「三史」と称されることもあった[35]。ただし、旧中国においては、『史記』よりも『漢書』が圧倒的に優勢であり、『隋書』経籍志の記録によれば『漢書』に比べて『史記』の注釈は非常に少ない[36]。
本文の信頼性
現存する『史記』の完本は南宋の慶元2年(1196年)のものが最古であり、これが司馬遷の原作にどの程度忠実かは大きな問題である。
唐代の作である「三皇本紀」は別にしても、太史公自序にいう「今上本紀」が今の『史記』には見えず、かわりに「孝武本紀」があるが、これが後世の補作であることは明らかである。それ以外の巻にも司馬遷が使ったはずのない「孝武」「武帝」の語が散見する。それどころか「建元以来侯者年表」「外戚世家」「三王世家」「屈原賈生列伝」には昭帝まで言及されている。とくに「漢興以来将相年表」は司馬遷のずっと後の鴻嘉元年(紀元前20年)まで記している。
『漢書』司馬遷伝によると、班固の見た『史記』は130巻のうち10巻は題だけで本文がなかった。現行本は130巻全部がそろっているので、後漢以降に誰かが補ったということになる。張晏によると、欠けていたのは「孝景本紀・孝武本紀・礼書・楽書・兵書・漢興以来将相年表・三王世家・日者列伝・亀策列伝・傅靳蒯成列伝」であるという。『史記』太史公自序の『索隠』は、このうち兵書は補われず、かわりに律書を加えたとする。
文学的価値
歴史叙述をするための簡潔で力強い書き方が評価され、「文の聖なり」「老将の兵を用いるがごとし」と絶賛されたこともある。特に「項羽本紀」は名文として広く知れ渡っている。
文体は巻によって相当異同があることも指摘されており、白川静は題材元の巧拙によって文体が相当左右されたのではないかと考えており、司馬遷自身の文学的才能には疑問を呈している。
歴史学的価値
正史として歴史的な事件についての基本的な情報となるほか、細かな記述から当時の生活や習慣が分かる部分も多い。特に「書」に記された内容は、前漢時代における世界観や政治経済、社会制度などについての重要な資料である。また、匈奴を始めとする周辺異民族や西域についての記述も、現在知られている地理や遺跡の発掘などから判明した当時の状況との整合性が高く、これらの地方の当時を知るための貴重な手がかりとなっている。また、秦始皇本紀における「始皇帝は自分の墓に近衛兵三千人の人形を埋めた」という記述についても、西安市の郊外の兵馬俑坑の発見で記述の正確さが証明されている。
一方で、『史記索隠』が引く『竹書紀年』などとの比較から年代矛盾などの問題点が度々指摘されている(例えば呉の王家の僚と闔閭の世代間の家系譜など)。宮崎市定は、『史記』には歴史を題材にした語り物・演出が取り込まれていることを指摘し、全てを実録とは信じられないとしている[37]。小川環樹は、司馬遷は『戦国策』等の記述をだいぶ参照しているであろう、とその著書で指摘し[38]、加藤徹も司馬遷が記した戦国七雄の兵力には多大に宣伝が入っているのではないかとしている。
注釈
- ^ 「太史公自序」では、司馬氏はもともと周の史官であったとするが、実際には春秋時代以前の司馬氏の来歴については信頼できない。司馬遷の祖先のうち、最も早く史実である可能性が高いものは、紀元前4世紀末に少梁に居住した秦人であったという記録である(吉本1996、p.193)。
- ^ 現行の「孝武本紀」は司馬遷の手によるものではない。「太史公自序」によれば、司馬遷の手による「今上本紀」が存在していたことは分かるが、早くに亡佚している。現行の本紀は前漢の褚少孫が補作したものとも言われるが、内容が「封禅書」の大部分をそのまま採録したものであり、褚少孫の補作ですらないとする見解(清の銭大昕)もある。
- ^ 増田欣『『太平記』の比較文学的研究』p112-p125(角川書店、1976年)の算出方法による。また、『太平記』章段の事書は西源院本に基づく。なお、例えば楚漢の興亡が『平家物語』・『平治物語』・『源平盛衰記』で紹介されているように、種々の軍記物語が『史記』にみえる説話を用いている。しかし、『史記』のテキストとの比較により、これらの軍記物語と『史記』との直接的関連を否定するのが通説的見解のようである。増田・前掲書p207以降。『平家物語』につき、山下宏明ら編・軍記文学研究叢書5『平家物語の生成』p129(汲古書院、1997年)。
- ^ 川瀬一馬『足利學校の研究』p32(講談社、1974年)。もっとも、『史記』は足利学校で教材とされる唯一の史書であり続けた訳ではなく、享保13年(1728年)の蔵書目録には『両漢書』・『通鑑』などがみえる。同書p167・p253。なお、「三注」とは『古注蒙求』・『千字文注』・『胡曾詩註』をいう
出典
- ^ 川勝 1973, pp. 7–10.
- ^ 川勝 1973, pp. 31–33.
- ^ 川勝 1973, pp. 34–38.
- ^ 川勝 1973, p. 39.
- ^ 川勝 1973, pp. 39–41.
- ^ a b 青木 1984, p. 176.
- ^ 川勝 1973, p. 65.
- ^ 増井 1987, p. 9.
- ^ 川勝 1973, p. 41.
- ^ a b c 吉本 1996, p. 125.
- ^ 川勝 1973, pp. 46–47.
- ^ 吉本 1996, p. 140.
- ^ 吉本 1996, pp. 220–221.
- ^ 吉本 1996, pp. 159–160.
- ^ 吉本 1996, pp. 73–79.
- ^ 吉本 1996, pp. 184–185.
- ^ a b c d e 米田 & 永田 1983, p. 118.
- ^ 吉本 1996, pp. 186–187.
- ^ 吉本 1996, p. 187.
- ^ 増井 1987, pp. 19–10.
- ^ 内山 2003, pp. 17–18.
- ^ 青木 1984, pp. 176–177.
- ^ a b c d 宮崎 1979, pp. 18–19.
- ^ 水澤 1984, pp. 163–164.
- ^ 吉川 2010, pp. 15–16.
- ^ a b c 吉本 1996, p. 216.
- ^ a b 川勝 1973, pp. 28–29.
- ^ 吉本 1996, p. 220.
- ^ 川勝 1973, pp. 56.
- ^ 川勝 1973, pp. 58–59.
- ^ 宮崎 1979, p. 150.
- ^ a b 宮崎 1979, pp. 20–22.
- ^ a b 吉本 1996, p. 211.
- ^ a b c d 吉本 1996, p. 213.
- ^ 吉川 2010, pp. 10–11.
- ^ 吉川 2010, pp. 8–9.
- ^ 宮崎 1979, p. 191.
- ^ 史記列伝・解説
- ^ 岡田正之『近江奈良朝の漢文學』p26・p62(養徳社、1946年)。
- ^ 指定文化財|国宝|史記孝文本紀第十(宮城県)
- ^ 『日本国見在書目録』の撰述時期は、未確定だが、本項では大庭脩『古代中世における日中関係史の研究』p299(同朋舎出版、1996年)を参照。
- ^ 中西進・厳紹璗編『日中文化交流史叢書 第6巻・文学』p207(大修館書店、1995年)の算出方法による。
- ^ 福井保『紅葉山文庫』p39(郷学舎、1980年)。
史記と同じ種類の言葉
- >> 「史記」を含む用語の索引
- 史記のページへのリンク