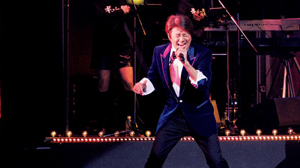ヒットを打ったのに処分? 「星野君」の罪と罰を考える
少年野球で監督のバントの指示に従わなかった選手がメンバーから外される「星野君の二塁打」という児童小説がある。道徳の教科書にも使われているが、「監督への服従の押しつけだ」との批判も多い。戦後すぐに書かれた定番教材で描かれる「罪と罰」を、どう読めばいいのか。奈良女子大学の教員4人が今春、体育学や心理学、倫理学などの観点から考える本を出版した。
集団生活でのルールを考えるための道徳教材として長く使われている「星野君」。2018年にあった日大アメフト部の悪質タックル問題を機に、注目を集めた。アメフト部の監督からの指示の有無が大きな社会的関心を呼んだことで、指示に背いた選手が処分されるこの作品が「軍国主義的だ」と批判された。
奈良女子大の教員4人が、そんな批判を学術的に分析し、作品の教育現場での使われ方を考えたのが「『星野君の二塁打』を読み解く」だ。
「規則の尊重」「集団生活の充実」――。「星野君の二塁打」は、今も道徳の教育現場で使われています。研究を続ける専門家は、どう考えるか。記事後半では、編著者へのインタビューもあります。
たとえば天ケ瀬正博教授(心理学)は、戦中のナチスに触れる。多くのユダヤ人を強制収容所に送り込む責任者だった官僚アイヒマンは、逮捕後の裁判で「祖国の法と旗に従っただけ」などと無罪を主張した。これを例に、「単に規則だから、みんなで決めたことだから、星野君は守らなければならなかった」と読解させてしまうと、子どもたちが自ら考えることなく集団に同調し、権威に服従するようになってしまう危険性があると指摘する。
米津美香助教(教育学)は、原作版と教科書版の違いに着目した。処分を言い渡された星野君が「異存ありません」と答える原作版に対し、教科書版はその発言が削られ、「うつむいたまま」で話が終わる。この変更を米津助教は「学習者に対して葛藤を生じさせ、特定の道徳的価値を導く」ものだと説明。その上で、「『教育効果』を高める一方、本来、原作が持っていた広がりや多様性を矮小(わいしょう)化してしまう可能性がある」と述べる。
出版を提案した功刀(くぬぎ)俊雄教授(体育学)によると、4人は執筆前、「どのように読むべきか」という議論をあえてしなかった。取材に対し、「まとまりに欠けるかもしれないが、その分、多面的に考える材料になると思う」と話した。
「『星野君の二塁打』を読み…