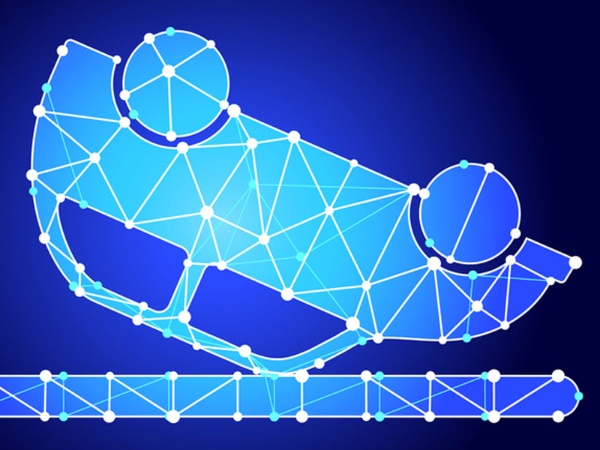戦後日本の「食品三大発明」とは何か。答えは「即席めん」「レトルトカレー」、そして「カニカマ」だといわれる。スケソウダラなどのすり身から加工される「カニ脚のようなかまぼこ」は1970年代前半に、魚介類を世界のどこよりも多く消費していた水産王国・日本で生まれ、その後10年ほどで世界中の食卓に浸透していった。水産資源を守る代替食の観点からも注目されることになるこの一大イノベーションは、石川県の能登半島から始まった。(文中敬称略)

まもなく11月6日、香箱ガニ漁の解禁日がやってくる。北陸地方などで水揚げされるメスのズワイガニのことだ。漁期が12月29日までの2カ月弱と短いこともあり、まさに“旬の味”。小ぶりながらジューシーで内子(卵)がギッシリ詰まった高級ガニは、国内外の食通をうならす。
「その香箱ガニの、最もジューシーな身が詰まったカニ脚を、カニにありがちな個体差によるハズレなしで、一年中いつでも楽しめるようにと開発したのがカニカマの『香り箱』です」
製造するのは石川県七尾市に本社を置く水産加工品メーカー、スギヨだ。管理本部経営企画室の田畑梨杏里は自信をもって説明する。カニカマとして限りなく「本物」と同等の味と姿、食感を追求。それでいて価格は1パック12本入りが398円(税別、希望小売価格)。大手コンビニエンスストアが「香り箱の寿司」として商品化するなど、高級感を出せる具材としても使われている。
国内だけでなく、海外でもカニカマは人気だ。カリフォルニアロールや太巻きのような巻きずしには必ずと言っていいほどカニカマが入る。日本かまぼこ協会(東京・千代田)によると、カニカマの国別消費量で1位はフランス、2位がスペインで、3位が日本だという。世界全体で、カニカマは約60万トンの消費量があるといわれる。
その欧州市場に供給する生産国として、日本を超えて世界一となったのがバルト3国の一つ、リトアニアだという。ヘルシーで良質のタンパク源であるという世界的な健康志向にマッチしたうえ、80年代にBSE(牛海綿状脳症)禍が世界的に拡大したことで「安全なシーフード」として普及が進んだ。カニの乱獲を防ぎ、資源管理をしているスケソウダラを原料に使うカニカマは、水産資源の保護を訴えるSDGs(国連の持続可能な開発目標)を40年以上前から実行してきた先行事例でもある。
このカニカマを日本で初めて商品化したのがスギヨだ。1972年に発売した、ほぐしたフレーク状のカニカマをパックに詰めた「かにあし」が、世界を魅了したカニカマの源流となった。
人工クラゲ作りの試行錯誤から生まれた「かにあし」
スギヨのある七尾市は能登半島の中央部東側にあり、能登島を抱いた七尾湾は古くから天然の良港として水産業の拠点となってきた。スギヨは、1640年にここで網元として水産業を営み始めた杉野與作が屋号「杉與(すぎよ)」を使い始めたのが発祥という。
カニカマ発明の原点は「人工クラゲ」の開発から始まった。当時、中華料理の珍味として利用されていたクラゲを、70年代に入って中国が輸出禁止にした。そこで、珍味が得意だったスギヨに「人工のクラゲを作れないか」との依頼が舞い込んだ。

当時のスギヨを率いていたのは3代目社長の杉野芳人(故人)。食に対して常ならざる興味と好奇心、そして執念を持っていた人物として石川県内でも有名だった。自分が食べたものについては必ず、内容や感想を常に持ち歩いていた手帳に細かく記していた。あと数分で列車が出発するというときにも、駅の近くに見知らぬ食堂やそば屋を見つけると、どうしても立ち寄って食べてしまうほどだった。
人工クラゲに商機を見てとった芳人は、研究所を設けてコンブ粉末などから抽出したアルギン酸ナトリウムや卵白、塩化カルシウムなどを使って、クラゲに近い食感の商品を開発した。だが、調味料であえると溶けてしまう。試行錯誤を重ねているうちに、中国のクラゲ輸出は再開されてしまった。
ただ開発中に、食べた瞬間に「これは、まるでカニだ」という作り方を発見していた。クラゲとしては失敗だったが、細かく刻んだ繊維もカニの脚の身に似ていて、風味や味覚は極めてカニに近かった。
「これをアルギン酸ではなく、本業のかまぼこで作ったらどうだろうか」。かまぼこを使えば調味料で溶けることはない。「これはすごい商品になるのでは」――。喜び勇んだ芳人は、人工クラゲ開発を中断して、カニ風味かまぼこの開発に舵(かじ)を切った。
技術開発担当の生産課長(当時)の清田稔に様々なアイデアを投げかけては、二人三脚で試作を続けた。繊維状の身を束ねればカニ脚のようにもなる。ただ、清田らが既存の製造機など全てを工夫して試作している現状では、カニ脚のように棒状にすると商品化に時間がかかると思われた。
「それじゃ売れない」が一転、トラックから奪い合うほどのヒットに
そこで、カニの身をほぐしたような「カニのようでカニでない、かまぼこ」として売り出すことにした。芳人や清田らとともに、この商品が「売れる」と直感したのがスギヨの営業担当、宮崎忠巳だった。宮崎は、当時スギヨが協賛していた相撲部屋の力士と一緒に酒を飲んだとき、力士の方が先に酩酊(めいてい)して動けなくなり、それを背負って部屋に連れて帰ったという酒豪で、全国各地のグルメにも詳しかった。
「カニは世界中どこでも高価だ。その代替品になる安価なかまぼこは、日本だけではなく世界にも通じるはず。外国人はかまぼこの柔らかい食感が苦手だが、このフレークなら受け入れられる」

そんな確信を持って東京・築地の中央卸売市場のほか、全国の水産加工品問屋に新商品「かにあし」を売ろうと、宮崎は独り歩き回った。しかし、「刻んだかまぼこ? そんなの売れないよ」と門前払いに遭う日々が続いた。途方に暮れかけていたとき、築地の場外市場に店を構えていた水産品問屋の合食(東京・中央)が「これは面白いかもしれない」と扱ってくれた。最初はこの合食がただ1社、売り出したという。
その日から世界が変わった。2カ月ほどで、店に並べた瞬間に売れていく商品となり、今度は築地市場の場内で扱う商品として引き合いが急に増え出した。その数、1日に5トントラックで5台分。「当時の運転手さんの間では、『築地に着いた途端に仲卸さんが我先にと荷物を降ろして持っていくので、自分で積み荷に触れる必要がなかった』という逸話も残っています」と経営企画室の田畑は語る。

その後製造機械を工夫し、フレーク状のかにあしを魚肉のすり身でカニ脚状に結着させた「ゴールデンかにあし」を開発、75年の年末に発売した。この商品はカニ消費地の北海道で最も売れる人気商品となり、後に米国でテスト販売されて、カニカマが世界に広がっていくきっかけとなっていく。
スティック状カニカマの製造装置を開発した大崎水産

スティック状のカニカマでは、広島県の大崎水産(広島市)が先行した面もあり、同社も「カニカマの元祖」を名乗る1社だ。大崎水産の発祥地である広島市西区草津は、片渕須直監督によってアニメ映画化もされた漫画家・こうの史代の名作『この世界の片隅に』のゆかりの地(主人公・すずの祖母が住んでいた土地)で、江戸時代から、のりやカキの養殖が盛んだった。
1928年にこの地で創業した大崎水産は2代目社長の大崎勝一がアイデアマンで、様々な珍味を開発してきたことが「カニカマのイノベーション」の発端となった。
機械にも明るく自ら製造機器を作っていた勝一が考えた商品に、キュウリの中にカニ肉を詰めて魚肉のすり身で覆う「かに胡瓜」という商品があった。
その製造途中で、すり身にカニのエキスが混じる。「これを使えば、カニ肉の代わりになるような商品を作れるのでは」と考えた勝一は、かつて開発したことがある魚肉そうめんの要領で、カニ味のすり身をシート状にしてから、細い繊維状になるように切っていく手法を考案した。
これを赤い色素で着色して、スティック状にして74年に発売したのが「カニスチック」だ。その後、名称を「フィッシュスチック」に変更したが、これが世界的にも最も一般的な形状をした「スティック状カニカマ」の原型になっていった。
ただ、一定の大きさと形状でカニカマを棒状にそろえるのは難しく、当初は手作業が必要だった。そこで機械好きだった勝一は、これを量産できる製造装置の開発にも心血を注いだ。そうめん状のすり身をまとめ、固め、赤い色素を均等に吹き付ける。その一連の工程を機械化して、自動的に繊維状のすり身を集束する製造装置を78年に完成させた。

スギヨがフレーク状の「かにあし」で売り上げを伸ばし、75年から棒状の「ゴールデンかにあし」を投入する中、大崎水産の「フィッシュスチック」の売れ行きにも徐々に火がついていった。76年度に5億円程度だった大崎水産のカニカマ売上高は、全自動の製造装置が完成した78年度には倍の10億円、82年度には40億円にも達した。
おでん種などが中心の練りもの製品は需要期の中心が秋から冬。だが、カニカマは単なるカニの代替品ではなく、サラダなどにも使いやすい通年で売れる商品となった。70年代後半からはかまぼこメーカーや水産大手が次々と参入し、各社の加工品事業の収益に大きく貢献した。
その中で、スギヨと大崎水産の“元祖”2社は、早くから海外市場にも果敢に挑戦した。すり身という水産加工品を高度に天然のカニに似せたカニカマは、ほどなく世界の食卓へも広がり始めていく。
(後編に続く)
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。
この記事はシリーズ「世界を変えた日本発イノベーション」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。