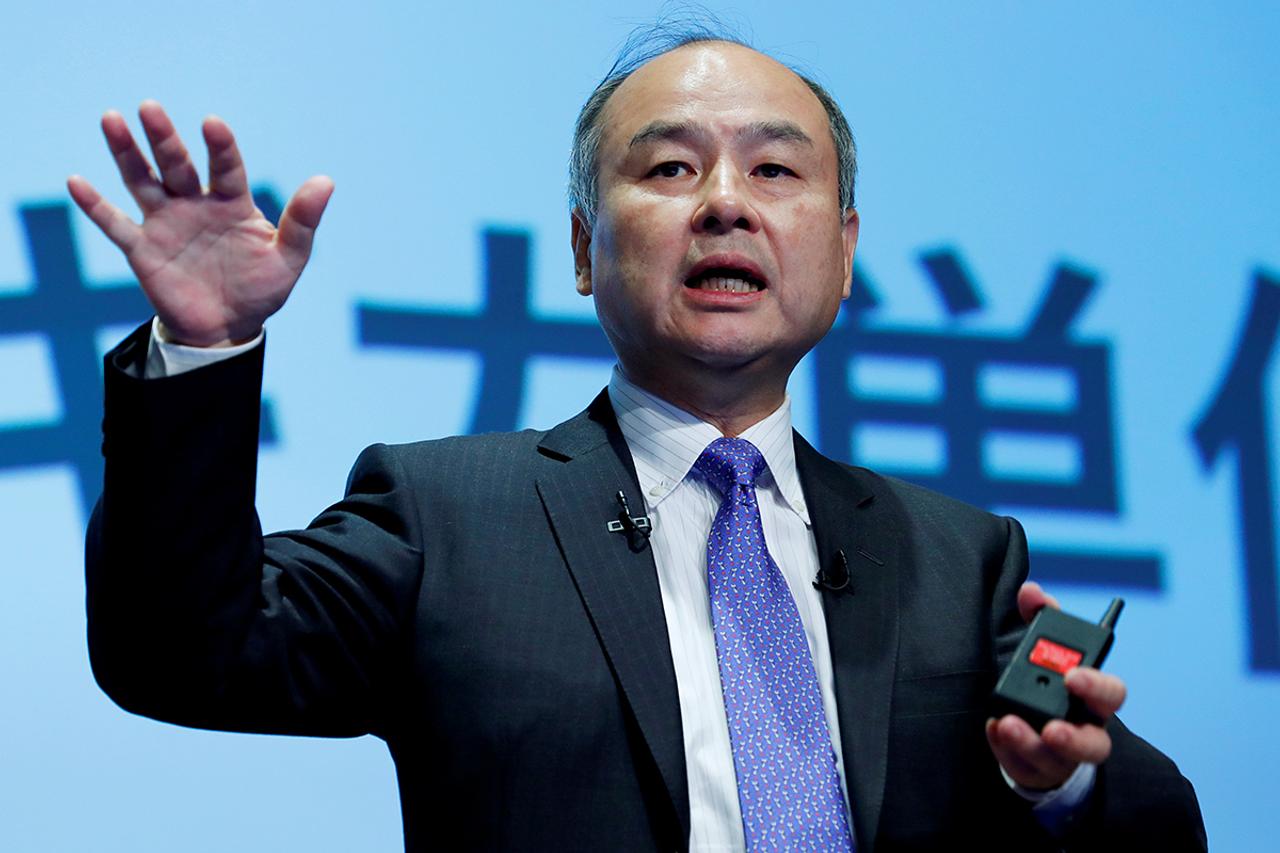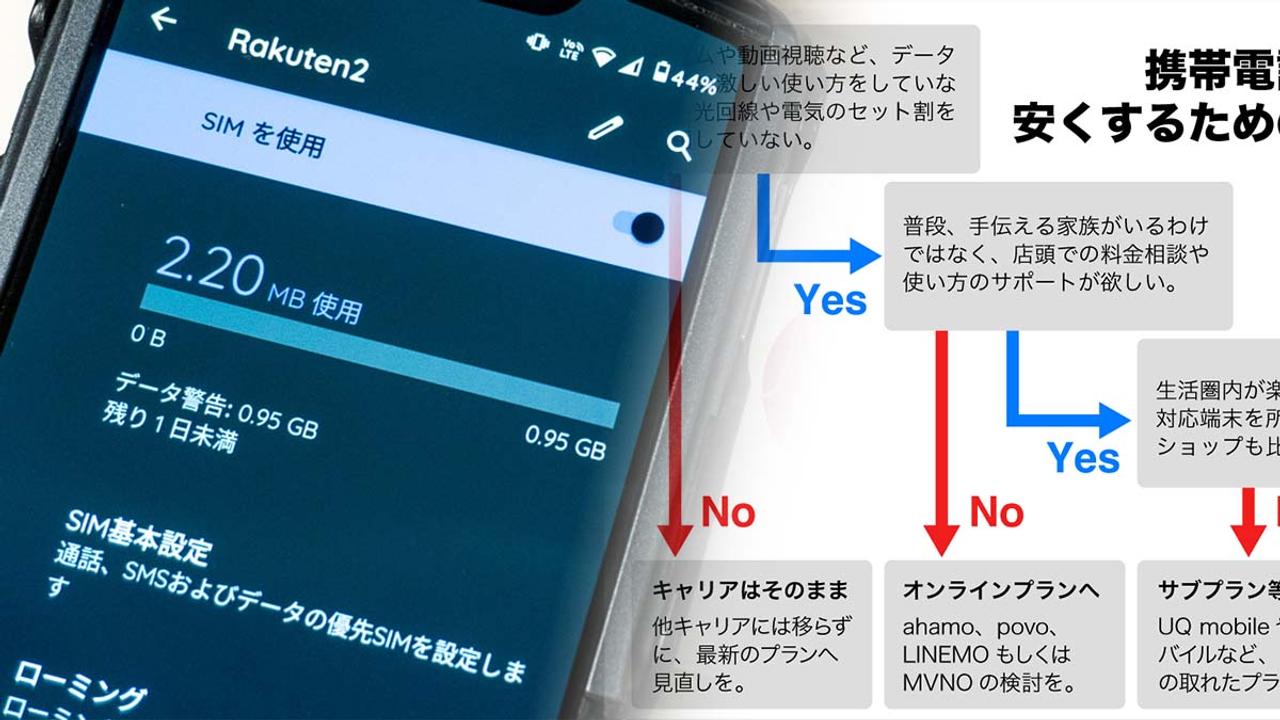NTTドコモ「ahamo」の登場など、日本の携帯料金は大きく下がった。
撮影:小林優多郎
スマホ料金の値下げ競争が終焉を迎えそうだ。
各キャリアとも「値下げ議論は一段落」と見切りをつけ始めたのだ。
KDDI髙橋誠社長は「値下げやマルチブランドに関する競争は各社ともに一息ついた感がある。これからは5Gの展開に軸足を移し、DXを勧めることで付加価値を高めていきたい」としている。
実際のところ、菅政権発足時には日本は「世界で2番目に高い通信料金」と指摘されていたが、いまでは世界で最も安い通信料金となっている(ICT総研調べ)。

ICT総研「2022年1月 スマートフォン料金と通信品質の海外比較に関する調査」より。
出典:ICT総研
NTT澤田純社長は「政府が国際的な料金比較をすると日本は高いということで値下げ競争を加速してきた。結果として、世界一の安さが実現した。そういう意味では競争はいったん息をついたということになる。基本的に競争は続けていくものの特異な値下げはいったん終えた」と振り返る。
政府の圧力による値下げ競争は見切りをつけ、早く企業間同士の健全な競争体制に戻したいというのだろう。
「料金値下げ」と「5G」キャリアが抱える危機感
各社が値下げ競争に「一息つきたい」と本音を漏らすのは、想像以上に通信料収入が悪化しているからだ。
ソフトバンクでは値下げのマイナス影響は4〜12月で490億円に達した。同社の宮川潤一社長は「通期では700億円を少し超える水準としていたが、見通しの範囲内」としている。

KDDIの髙橋誠社長。
出典:KDDI
一方、KDDI髙橋社長は「値下げによる収益減を年間で600〜700億円と見積もっていたが、詳しい額は言えないものの、見込みよりも減収幅が膨らみそうな状況にある」と語る。
値下げを進めたことで心配されるのが、設備投資への悪影響だ。このまま値下げ状態の通信料収入となれば、次世代に対する設備投資を抑えていく必要があるからだ。
ソフトバンク宮川社長は「4Gから5Gに移行することで通信料金が下がった。もし、料金が値下げしたままの状態で日本だけがしゃかりきになってインフラをつくると、収益効率の悪い国の代表例になる。そうすると日本に新しい技術があまり寄ってこなくなる危険性もある」と警鐘を鳴らす。
KDDIとソフトバンクではネットワークへの設備投資を10年間で2兆円規模、見込んでいる。しかし、通信料収入の減少が続けば、そうした設備投資計画を見直す必要も出てくるかも知れない。

ソフトバンクは2021年度第3四半期決算の翌日である2月4日に「5Gの人口カバー率が85%超に、基地局数が2万3000局超」と正式に発表した。
撮影:小林優多郎
宮川社長は、
「2022年の設備投資計画は2021年とさほど変わらないぐらいを見込みたい。5Gの基地局は全国で最低5万局は必要で、いまは2万3000局ぐらいなので、数年かけて面をつくる。それからトラフィック分散をかけていく。
しかし、通信料収入が下がる中で、同じCAPEX(設備投資)の計画をして、同じ運用コストをかけるのであれば収益性は崩れてくる。バランスを見極める必要がある。将来的には5G投資のほうが4G時代よりも減ることは充分にあり得る」
と言う。
もともと、KDDIとソフトバンクは4Gで使っている周波数帯を5Gに転用することで、5Gエリアを広げるということをしている。飛びやすい電波でエリアを広げつつ、通信トラフィックが発生しやすいところには集中して5G用に割り当てられた周波数帯を使うというわけだ。
KDDI髙橋社長は「2021年度末に人口カバー率90%台に持って行きたかったが、オミクロン株や半導体不足の影響もあり、遅れが出てしまっている。2022年度のできるだけ早い時期に達成したい」と語る。
ソフトバンクは再び「Wi-Fi」に注目

ソフトバンクの宮川潤一社長。
出典:ソフトバンク
面展開においては目処が立ちつつあるものの、将来的に通信トラフィックが爆発的に増えることが予想される。
一方で、設備投資にお金はかけられなくなる可能性もある。そんな中、宮川社長としては5Gではなく、Wi-Fiを活用するアイデアも浮上しているようだ。
「最近はWi-Fi 6、2023年ぐらいにはWi-Fi 7という規格が誕生してチップセットも出てくる。5GはSA化するとコアの設備が5G専用になり、いろいろなことがやれるようになる。
ここ数年だけでいくと、インドアの莫大なトラフィックを5G側に寄せるか、Wi-Fiに寄せるかなど、さまざまな戦略をとれる。我々がやりたいサービスや、つくりたいネットワークは何なのかを議論しているところだ」(宮川社長)
かつて、ソフトバンクはiPhoneユーザーが増えたのはいいが、通信が混雑し、速度が低下したり、プラチナバンドがないためにエリアカバレッジがイマイチだったりした際に、街中に公衆Wi-Fiスポットをつくりまくるという奇策で乗り切ったことがあった。
まさに同じ状況が5G時代にもやってくる可能性が出てきたというわけだ。
NTTは「真の5G」を押し進める

写真中央がNTTの澤田純社長。
出典:NTT
一方で、「真の5G」にこだわるのがNTTグループだ。NTTドコモは4Gの周波数帯転用を水面下で準備しているようだが、正式コメントとしては「導入時期は検討中」という。
NTTの澤田純社長も「政府が目標に掲げている人口カバー率はもちろん上げるべきだが、4Gを使った5Gではなく、5Gを体験できる、5Gそのもののサービス展開をすべきだと考えている」としている。5G向けに割り当てられた周波数帯を中心に、5Gエリアを構築していくのが基本的なスタンスのようだ。
ただ、5Gらしさを体験できるサービスやコンテンツに関して澤田社長は「2年以上、待つ必要がある」としている。
値下げによる通信料収入が激減する中、次世代に向けてどんなネットワークを構築して、5Gらしいサービスを提供していくか。今後、各キャリアで戦略の違いが見えてきそうだ。
(文・石川温)