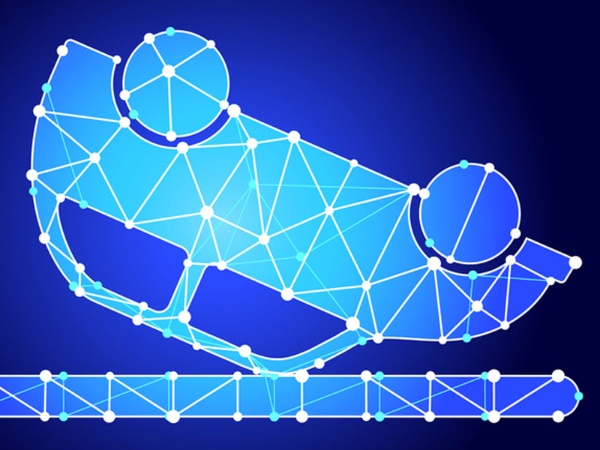※2008年6月5日に日経ビジネスオンラインで公開した記事を再掲載しました。記事中の肩書きやデータは記事公開日当時のものです。
現代の脳外科医、南方仁は、ある夜突然幕末時代の日本へタイムスリップしてしまう。そこで見たのは、現代から見れば劣悪な環境と医療技術の中で、したたかに生きていく江戸時代の市井の人々。そして、改革期の日本を支える勝海舟、坂本龍馬、西郷隆盛らとも出会う。仁は、自らが持つ医療技術を約130年前の時代に普及するべく、仲間たちと共に死力を尽くす…。破天荒な設定と重厚な筆力が織りなす異色の医療ドラマ『仁-JIN-』、累計100万部を超えたシリーズ最新刊の発刊を期に、筆者の村上もとか氏にインタビューした(聞き手は日経ビジネスオンライン副編集長 山中浩之)
(C)Motoka Murakami 2008 /集英社
―― 村上もとかさんのマンガは、すごく描き込んだ絵のリアリティーと設定の上に、とても気持ちのいい主人公がいて、ライバルがいて、ヒロインがいて、その人間関係の中で「技」に打ち込んでいくことを通して、登場人物たちが成長していく…そんなイメージを勝手に持っていました。
ところが、今回お話を聞く『JIN(仁)』は、村上節はそのままに「あり得ない話」にぽーんと飛ばしましたよね、「現代の脳外科医が、江戸末期にタイムスリップする」という。リアルに幕末の時代を描きながら、そこに現代の主人公を置いてみようと考えたのはなぜなんでしょうか。荒唐無稽を承知で何をおやりになりたくてこういうことをなさったのかというのが、すごく聞きたいんですけれど。
あえて破天荒な設定、その理由は
村上 もともと江戸時代、特に幕末の時代にすごく興味があったんですね。ロケットで宇宙の果てを見せてくれる、といわれても「それができるなら、タイムマシンで1日江戸時代へ行きたいな」というくらいで(笑)。チャンバラとかいうことじゃなしに、「どんな生活を送っていたんだろう」ということでね。
幕末というのは今から3代か4代ぐらい前、長くたって5代前ですから、そこで暮らしていた人の名前から確実に分かるご先祖さんたちが、生きていたわけですよね。そして、あの時代の環境というのは、実は非常に平均寿命が短い。本当に今だったら簡単に治りそうな病気で、ほとんどの人が亡くなってしまう。
―― なるほど。

1951年生まれ。高校2年の時、漫画雑誌「COM」の影響を受け、漫画を描き始める。1972年「少年ジャンプ」でデビュー、1977年、「少年サンデー」で『赤いペガサス』がヒット、81年には『六三四の剣
一方で、江戸期には華やかな文化も存在している。いったい、どういう気持ちで生きていたんだろう。そう思って幕末の医療についても読んだりしていたんですけど、それはもう小説や漫画でもいろいろな形で描かれてる。「自分が新たに描くとしたら、どんな切り口から描けばモチベーションを高めることができるだろうか」とは、ずっと思っていたんです。
そんなときに幕末の、いわゆる花魁や遊女たちの性病にポイントを当てた本を見つけたんですよ。『江戸の性病~梅毒流行事情』(苅谷春郎著)という本です。読んでみたら、ものすごく平均寿命が短いんですね。
そういう職業に就いている人たちは、性病にもなるし、結核にもなったりとかする。もっとも条件のいい吉原などで25歳、条件の悪いところだと20歳そこそこの平均寿命だと。幸運に仕事を辞めるまで生き延びた人がいたとしても、その後、すぐに病気で亡くなっちゃったりするわけです。
それを知ったときに、とてつもなく悔しい思いがしてきて。その悔しさを晴らすにはどうしたらいいんだろうなと。タイムマシンで当時に行けても、自分は別に医療従事者じゃないし、何もできない。ああ、俺がもし医者だったら、そういう時代に行って治してあげたいな、というぐらいの気持ちになったんですね。
―― え? 気持ちになられて、それでどうされたんでしょうか。
当時の本を読んでいる素人が悔しくて仕方ないくらいなんだから、本当のお医者さんがこの時代に行ったらどういう気持ちになるだろうか。といっても設備も人材も現代とは違うんだから、何をどれだけ助けることができるんだろうか、ということでイメージが膨らんできて、それで、本当のお医者さんに実際に――「荒唐無稽な質問なんですけど、もしあなたが江戸時代にタイムスリップしたらどうしますか」とお聞きしてみました。そうしたら、みなさん、「えーっ」と。
―― それはそうでしょう…。
でも出会った先生が、みんな大変面白い先生で、すごくうまく答えていただきまして、「たとえ現代と同じ医療器具や薬はなくても、できることはいっぱいいろいろあるからね」と。「江戸時代でも、自分たちが今まで学んできたことを生かせば、専門外のことでもやることはいっぱいあるはずだ」という言葉に背中を押されて、よし、大変だけどこれをやってしまおうと。
私は別に時代劇に特別に詳しいわけじゃなかったですし、もちろん現代医療のことは知りませんし、幕末医療のことだって、そんなに本格的に知っているわけじゃありません。でもそれらを全部ちゃんとチェックしていただける専門の方をつけさえすれば、後のタクトは自分が振ってみたいと。
(C)Motoka Murakami 2008 /集英社
―― 作品の中で驚くのは、麻酔手術はもちろん、ガンの切除まで「当時の技術」と「現代のスキル」の組み合わせで、やってのけてしまう。そこになぜか、異様なリアリティがあるところです。
例えば、世界に先駆けて華岡青洲は麻酔に似たものを開発したりとか、そういうところの創意工夫、日本人の必死の、世界的な水準でいったら決して高くはなかったかもしれないけど、そこはしっかり踏まえたいんですね。鎖国体制を取りながらも、実は長崎を介して学問なり、技術が入ってくる道を作っていた。その中で一番世の中に直接役に立ったのは、医学ですね。蘭方でオランダを通じて入ってきた医学というのは、すごく大きくて、江戸の250年の中に、ちゃんと脈々と積み重なってきて、知の財産として積もり重なって、幕末を迎える。もちろん最新の西洋医学ではないにしても、実際には相当、レベルが高かったんじゃないかと。
―― そういう歴史的な土台がなかったら、未来から医師がやってきても……
あそこまではできない、と言いますか、ああいうリアリティは持てないと思うんですよ。単に理解されないで終わると思うんですね。
時代の閉塞感から『龍-RON-』が、そして
―― 『JIN-仁-』を描き始められたのは2000年なんですけれども、この辺は経済の方からいきますと、1997年に都市銀行がつぶれ、4大証券の一角が崩れということで、これはいよいよ、悪いことは何でもありなんだなという閉塞感が濃くなってきたころですね。ITバブルでちょこっとだけ株価が上がるんですが、また落っこちてきます。
そしてこの年、かわぐちかいじさんが『ジパング』(講談社「モーニング」連載中)を始められました。昭和23(1948)年生まれと、村上さんよりもちょっとお年を召していらっしゃいますけど、こちらもタイムスリップものですね。自衛隊の最新鋭の護衛艦「みらい」が、太平洋戦争の最中に乗員もろとも出現する。2年ぐらい前にお話を聞いたことがありまして、こういう時代をつくってきた世代として、自分の中で責任を取りたい、という趣旨のことをおっしゃったんです。
かわぐちさんは自衛隊や政府という大組織を描くのがお上手ですしお好きですから、マクロな形でそういうことをおやりになっているんだと思うんですけれども、もしかしたら村上さんの場合は、個人という目線から、時代の閉塞感に触発されていらしたんではないか…。などと考えていました。でも、始まりはとてもシンプルなものだったのですね。
どちらかというと、時代的なものを意識して描いたのは、1991年の頭から始めた『龍-RON』(小学館「ビッグコミックオリジナル」連載)ですね。
僕は昭和26(1951)年に生まれて、高度成長に乗ってわーわーと、お祭りみたいな感じでもいたし、漫画も、ちょうど自分たちが描き始めたころというのは、社会的に影響力を持ち始めて売れるようにもなったし。「漫画家って貧乏なままみんな死んじゃうのかな」ぐらいに思っていたのが、漫画を描いても生きていけるんだという感触になった。
本当に、時代のおかげでこの職業でずっと食べてこられたなという感じもあったものですからね。それがバブル崩壊で、「世の中、もう終わりか」なんて雰囲気もあったけど、戦争の直後なんてこんなもんじゃない、もっとすさまじく悲惨だった戦争の後に、日本人はこれだけ復活した。もちろん社会的な様々な問題はあるけれど、比べたらまだどうってことはない。ゼロになったわけじゃないし、株価にしても単にバブル前に戻っただけですよね。
だったら、日本がすべてを失ったあの戦争直後、その前の時代って、何を持っていた、どんな時代だったんだろうというのが、『龍-RON』を描いた根本みたいな感じだったんですよね。
―― それでは、『JIN-仁-』は?
『JIN-仁-』を描いた背景には、株価と一緒にみんな右肩上がりでもう1つ伸びていったものがあります。日本人の寿命です。ぼんぼんっと上がっていった。
―― そうですね。
日本人は男性で70代後半、女性で80歳を超えるまでになった、世界一の長寿国だと。今、寿命が延びても延びても、不安も右肩上がりというか、不安と道連れで寿命が延びていっちゃう。長生きすればするほど、ずっと80歳、90歳になっても、まだ明日の健康を心配している、みたいなね。
―― 20歳、30歳で「俺たち老後どうするんだろう」と言いかねないですからね。
C)Motoka Murakami 2008 /集英社
それはよくないと思うんですよ、単純に考えて。
江戸時代の人は30年から40年しか生きないのに、楽しく遊んだり、あるいは必死に勉強したりしていたはずです。例外はあったでしょうけど、そうでなければあれだけの都市や文化、学問は残せなかったと思う。「どうせ人生なんて大したことないんだから、もう適当でいいや」ではなくて、ある意味あっけらかんと、かつ、ひた向きに生きていたんじゃないか。だったら、今の我々から見たら、すごいことだなとあらためて思ったんです。
―― 作中で、貧乏な家の子供を主人公が無理して診たけれども、手遅れで助からなかった場面がありました。力が足りず、すみませんと亡きがらを渡したときに、いや、診てもらえただけでありがたい、と母親は礼を言います。愛しい子供を救おうとしてくれた医者に、悲しい気持ちを抱きつつ感謝する。いいシーンだと心から思いますが、これ、今だったら医療過誤になりかねない雰囲気があります。
江戸時代なら美談でも、現代では医療過誤?
そうです。医療に限りませんが、心の距離がすごく開いている感じがする。
医学から見たら生物として生きるリスクが現在よりもはるかに高い江戸時代、そこに視点を持っていくことによって、主人公と、それを取り巻く人たちとの、医者と社会、命と社会というものとの関係をもっとシンプルに描ける。現代のものに持ってきちゃったら、言われたとおり、たぶんあんなふうに、シンプルに、先生、ありがとうございましたって感謝してくれないですよね。
―― その心の距離の開き方が、お医者さんのモチベーションをすごく下げていますよね。
そうですよね。文字で書いてこれこれの責任を取る、こういう場合には取らない、そういう複雑な約束事に頼る傾向が顕著になったのが、時代的な傾向なんでしょう。そして、偽装やら何やらで「書いたものも信じられないんじゃないか」となってきた。
実は日本人の平均寿命というのは、大正ぐらいまであまり変わってないんですね。飛躍的に延びていったのは、大正かららしいです。余談ですが、この間、養老孟司先生の話を聞いていたら、理由は水道の普及だと。医学が延ばしたというより、インフラの整備の方が大きいんだと。
人間というのは、ついこの間まで本当に「人生50年」というのが当たり前のことだったんですよね。それを今は人生80年、あと30年生きていかなきゃいけないということになった。で、どうしようと。これまではあまり考えてなかったんでしょうけど、ここからみんなに重くのし掛かってきている。
―― 主人公、仁は、50年なり、もっと短い中でけなげに――けなげという言い方も上から目線なんですが、明るく短い人生に立ち向かっていた人に、医者として手を差し伸べることで、自分自身も変わっていきますね。一方で、現代の世の中にいたときの、彼のやりがいとか、幸せとかについては、わざと描かれてないような気がするんですけど。
「面白かった」と思って死ぬ、そのために生きている

彼は、冒頭で恋人にはふられて(笑)。まあ、仕事はどっちかというとルーティンワークとしてやっている。ばりばり野望に満ちた『白い巨塔』の財前君のような感じは全然ない人間なんです。
だから全然、そんなに熱いものはなかったと思うんですよね。それが江戸時代に行って、初めて医者って何だろうということを考え始めた。江戸時代だから、医者が非常に個々の人間の人生に触れる。人と触れるということは、人の人生をいろいろ見て触れるわけです。そうなると、人の一生ってどういうことだろうな、この人は、自分は、何を幸せとして生きていくのかな、ということに結び付くのかなと思うんですよ。
やっぱり何だかんだ言ったって、お金が大変でも、経済がぱっとしなくても、日本人の80歳の平均寿命が、いきなり50歳や60歳に落ちることはないと思います。政府が変なかたちで年金を天引きしたからってね。まあ、みんな絶望して自殺を始めちゃったらそうなっちゃうかもしれないけど、そうでもない限りは全然減らないと思います。
だから問題は、この与えられた残りの人生を、どんなふうに面白く生きてやろうかなということを、みんなが考え始めるかどうか。そういうことじゃないでしょうか。そうしたら、すぐ経済にだっていいことがあるんじゃないかと。逆算するというか、もし80歳まで生きられるんだったら、自分はあとこれから…俺の場合だったら、25年間ぐらい何をやってやろうかなと。やっぱり「ああ、面白かった」と死にたい、みんなそうじゃないのかなと思うんですよね。
そのためにお金を使うし、そのために働きもするし、肩書きにこだわる必要もない。だって考えなきゃいけないことは「自分が面白がって生きて死ねるか」だけなんだから。そのために、必要に応じて働くということをみんなが考え始めたら、何か結構面白くなるんじゃないかな。もう一回、日本って変身できるんじゃないかな、と。
―― なるほど。となると『JIN-仁-』の話の中心になるのは、やはり個人の生き方なのでしょうか。砕いて言えば、自分が「ああ、面白かった」と死にたいなら、どう生きようか、という。
個々の1人の人間の幸せ、ということを考えると、それは本当に一人ひとり全部違うんだろうというのが、まっとうな答えなのかもしれないんですけれども、あえて村上さんに「こういうことが幸せだと思う」とお聞きしてみたいのですが。
それでは、幸せとは何か
難しいですね、こういうことが幸せ…。
―― というのは我々って「結局、俺は何が幸せなんだ」ということを、あまりまじめに考えないんだな、と最近よく思うんですよ。懐かしのホリエモンさんじゃないですけど、「ま、基本はお金だよね」というあたりで、どうも止まってしまうような。それが悪いというのではないけれど、例えば「じゃあそのお金で、何がしたいんだ」ということが分からない。「幸せ」については、お金の先にまだまだ先があるように思えて。
お金は手っ取り早い快楽ではあるかもしれないけど、幸せというものとはちょっと質が違う感じがするんですよね。じゃあ本当に、堀江さんのお金でもって、友情や愛情まで買えたのかといったら…。
―― そうなんですよ。「愛はお金で買えます、ただし時間制限付きです」というのが、たぶん正しいところで、「お金が切れたときにそれはなくなっちゃうんですよ、それでもいいんですか」という話になりますよね。
ひとつは、友達というのか、ご近所さんと言ったらいいのか、知り合いと言ったらいいのか分からないんですけど、そういう人間関係を、現役であろうがなかろうが、会えば、「ようっ」と言って話せる人間関係があること。それから、今思ったんですが、たぶん人間の幸せって「教養」だと思うんですよ。
教養のある人はたぶん不幸にならないと思うんです。僕は全然教養がないからだめなんで、焦っているんですけど。教養のある人というのは、たぶん本当に生きているぎりぎりまで、あの世に召されるまで楽しめるんじゃないかと思いますよね。教養こそ、やっぱり人生を楽しむすべなのかなと、技なのかなという感じがするんですね。
―― 教養というと、ものすごく敷居が高そうですが、おっしゃっているのは「どこそこの大学で教授になって」とか、そういう「手段としての」教養ではないですよね。
ええ。簡単に言えば、好奇心とか、段位が目的ではない習い事と言いますかね。「今まで知らなかったことをどんどん深めてみる」というのは、本当に楽しいこと。人間が人間であるが故の面白いところ。人間だからこそ持っている楽しみ方だと思いますよね。食べることとか、セックスをすることとかは、動物だったらそんなに違いはないわけです。お金を持っていれば、もうちょっときれいな女の人とできるとか、三つ星のレストランで食えるとか。でも、おなかがいっぱいになったらもう食べられない。
―― 死ぬ間際まではもちろん食えない(笑)。
否定するわけじゃないですよ。そういうもののよさはあるし、それはそれで文化として出される。だけれども人間がたった1人で、例えば死に向かうときに、知り合いがいなくたって、1人でぽんと置いていかれたとしても、ベッドの上で寝たきりでも、最後までぎりぎり、もし頭の中で楽しめることといったら、やはり人間的な教養というか、素養というか、そういうものなのかなと思うんですよ。江戸時代の人たちを支えていたものがあるとしたら、それじゃないでしょうか。
* * *
【赤いペガサス秘話】
―― さて、以下番外編です。おそらく日経ビジネスオンラインの読者の方には、中高生当時、村上さんの『赤いペガサス』(小学館「少年サンデー」掲載)を読んで、F1という世界を知った方もたくさんおられるのではないかと。連載開始の1977年は、ホンダの第2期参戦のずっと前のお話ですから。今回のテーマからは完全に余談ですけど、あのころいったいどういう経緯で『赤いペガサス』を始められたんですか。
(C)Motoka Murakami/小学館
村上 僕はデビューからしばらく「少年ジャンプ」でメカ物といいますか、車、バイク物を描いていたものですから、「この人はモータースポーツが好きなんだろう」というイメージを持たれていたんですね。実は僕は「少年サンデー」に移るときには、せっかく別の雑誌に移るんだし、違うものをやりたいと思ったんです。
ところが、移ったときはちょうど創刊20周年だったと思うんですよ。その記念で「10週だけでいいから、レース物を描いてくれないか」という話になったんです。「えーっ、またタイヤの付いたものを描くのか」と思ったわけ(笑)。
―― 村上さん的には「えーっ」だったんですか、私たちの大切なあの赤いペガサスが。
当時「ジャンプ」は、あのスーパーカーブームで沸いていた。クルマものなんて、柳の下のドジョウを2匹狙ったってしょうがないから、やる気はないと言ったんですけどね。
ところが編集の人が、「じゃあ、一番上のレースカテゴリーを描いてみないか、最上位はF1だ」と。そう言うならば、あなたはF1のこと知ってるの? と言ったら、「いや、知らない」と(笑)。
ただ、「どんなふうに描いても構わない。レースや練習でもって死んじゃうような話だって」…そのころは死ぬシーンなんてとてもタブーな話だったんですけど、「死んじゃっても構わない」と。とにかく読者の印象に残るようなものを描いてみないかという話だったんですよ。
F1というのはスーパーカーとはまったく違うカテゴリーだし、しかもストーリーとしても、まるっきり振り切ったような話でいい。プロットを話して「少年誌でこんなのをやっていいのか」と言ったら、別に構わないということだったので、「じゃあ、やります」となったんです。
―― そうなんですか。
意外と言っては申し訳ないのですが、読者の方々から実に熱い反応があって、続けることができたという感じですね(1977~1980年掲載)。いつ打ち切られても構わないというつもりで描いていたので。
F1なんて知らない!? でも「AUTO SPORT」の編集者が協力してくれた
―― ちょっとそれは衝撃ですね。村上さんは以前からF1の世界をものすごく深く知っていて、いよいよ描く場所を得た、というお話なんだろうなと勝手に思い込んでいました。だって、私はあれでF1好きになっちゃいましたからね。
そういう人がいっぱいいらっしゃいます(笑)。
―― 「AUTO SPORT」って、今でもありますけれども、海外のモータースポーツを紹介している、当時ほぼ唯一のシブい雑誌がありまして、クラスで回し読みしてました。あれを買うようになったのは『赤いペガサス』を読んでしまったからなんですよね。
ああ、「AUTO SPORT」を買っていましたか。実は、『赤いペガサス』の核になる部分や、F1の世界のディティールは、「AUTO SPORT」の編集さんが当時この連載に非常に目を掛けてくださって、情報をどんどんくださったんですよ。
―― えっ、「AUTO SPORT」が協力してくれていたんですか。
ええ。といっても、正式の業務ではなく、もう仕事は別にして、毎日、ご自分の会社から家に帰る途中に私たちのスタジオに寄って、いろいろな話をしてくれたんですよ、F1の。それがもう面白くてね。
―― それでああいう、「こういう世界なんだ」という生々しい描写が入っているわけですか。
ええ。
―― 相手チームのタイヤをむしって、コンパウンドを調べたりとかしますよね。
「チームの人は、そういうこともやるんだよ」とか教えてくれたんですね。あと、レーサーのいろいろな裏話というか、そういうものもそのままじゃ描けないから、じゃあ、この人に変えてみようとか。あのころのF1レーサーってみんなキレてるんだよね。もう絶対、ネジが1本や、2本なんてものじゃないですよ、ネジが全部飛んでいるような頭をしているからね。そういう話を聞くのが面白くて。
―― 驚きました。
もともと描きたかったのは少女漫画だったんですよ。少女漫画というとちょっと私とはイメージが違うのかもしれないけど、描きたかった雑誌を具体的に述べよといったら、「月刊セブンティーン」でした。「月刊セブンティーン」は、ちょうど僕が20歳ぐらいのころ、読み切りの「文芸路線」を採っていたんです。
「子供をばかにするな」と感じた違和感
いわば、小説を漫画でもって描いてみたい、という感じで、普通の少女漫画とも違う、かなり描き込んだ絵で。そのころはそんなものに憧れていまして「そういうものをほそぼそとやっていけたらいいな」みたいな、イメージを持っていました。
でも、もともとメカとか何かを描くのが、またそれはそれで好きだったんですね。メカ自身に興味はあったんですけど、ただ自分自身は免許を持ってないから、車も乗らないし、それを専門に描くとか何とかということはないだろうと思っていたんですけど、なぜか絵柄や何かがそっちの方に向いているんじゃないかみたいな、そっちの仕事が多かったです。
―― リアルさへのこだわりというのは、最初からお持ちなんですか。
わりとそうなんでしょうね。ただ、やっぱり挿絵画家に――僕は、本当は漫画家じゃなくて挿絵画家になりたかったものですから。小説に付く挿絵みたいなものを描いてみたいなと。というのは、子供ものに付いてくる挿絵は、平明な、簡単な、シンプルな、かわいらしいでしょうという絵でしたから、そういうのを見せられるのは、腹が立ってしょうがなかったんですよ、子供心に。
―― 子供をばかにするなと。
子供って、描かせるとある一点をごりごり克明に描いていたり、どろどろしていたり、結構すごいんだよね(笑)。「子供がみんな、こういう絵を見せられたら喜ぶというものじゃないよ」と思っていたものですから。
子供は子供で、何か読み取るんですよね。それだけ物を感じていて、グロいくらい細密な絵にひかれちゃう場合だってある。言葉を知らなくても、それこそエロチシズムと言っていいくらい、ものすごく気持ちを揺さぶられるものを感じたりとか。だから、お仕着せで「子供はまあこんなもんだよ」というのを出されたら腹が立った。もちろん当時の子供向けだって、この人の絵はすてきだなとか、この人の絵は何か楽しくていいなとか、そういうのはありましたよ。でも、子供のときに感じた違和感が、リアルさを志向する自分のベースには、あるのかもしれないですね。
(聞き手:日経ビジネスオンライン 山中 浩之)
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。
この記事はシリーズ「もう一度読みたい」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。