”防災の鬼”渡辺実氏は次のように語る。
「ゼンリン住宅地図の実物を見るとわかるけど、地図上に住宅など建物の形に加え、各家に住んでいる人の名前(名字)まで書き込まれています。これはゼンリンのスタッフが足で歩いて、表札を見て作っている。だから表札で公開されている個人情報を基にして名字を記載しています。こうした詳細な住宅地図を国民が自由に入手にできる国はありません。紛争地帯などに行くと、住宅地図などもってほのか、そんなもの民間が作ることはあり得ません。まさに地図は平和の象徴なのです」(渡辺氏)
実はゼンリンの歴史も、そうした思いに貫かれている。1948年創業のゼンリン。社名は隣国や近隣と親しくすることを意味する「善隣友好」に由来する。社名には創業者の「平和でなければ地図作りはできない」という思いが込められているのだ。
思いは日々形にされている。現在同社は全国の自治体と災害時支援協定を結ぶ取り組みを遂行中だ。
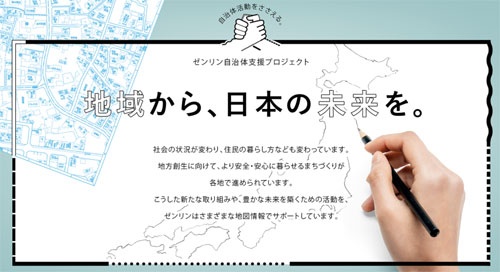
「協定内容の1つが『地図の備蓄』です。全国に1700以上ある地方自治体と協定を結んで、有事の際に必要となる地域の住宅地図5セットを箱におさめて備蓄してもらうのです。他にも通常使用が可能な広域地図5枚と、インターネット住宅閲覧サービスのIDもおつけします。『災害時支援協定』として、現在順次各自治体と協定の輪を広げています」(ゼンリン 上席執行役員 第一事業本部長の山本勝氏)
東日本大震災を教訓に2013年に始まった『災害時支援協定』は現在299自治体(2016年12月末現在)にまで広がっている。
ゼンリンのスタッフが全国の自治体を1つずつ訪ね、協定の意義について説明、趣旨に賛同してくれた自治体に住宅地図などを無償貸与するのだ。
ただし、ここで終わらないのがゼンリンのすごいところ。貸与した住宅地図は最新版が発行されれば取り替え続けるのだという。これをゼンリンは無償で行っている。
「東日本大震災で、地図は発災のその日、その瞬間に必要になるというのを学びました。ところが手元にない自治体が多かった。そうしたところから、少ないけれども、最新の地図を常にストックしてください、という“地図備蓄の協定”を始めたわけです」(山本氏)
熊本や糸魚川でも活躍
熊本市とは2014年7月にこの協定を結んでいたため、2016年4月に発災した熊本地震ではこのストックがおおいに役立った。
ひとたび災害が起これば全国どこにでも出没する”防災の鬼”渡辺実氏は、ゼンリンの住宅地図がどのように活用されているかその目で見て体感している。
「2016年の12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災の現場にも行きましたが、ゼンリンをはじめとする各種の住宅地図が大活躍していましたよ。あの規模の火災になると、どの家がどこにあったのかわからなくなり、誰がどこに住んでいたのかわからなくなる。住宅地図が安否確認に活用されていました。自治体職員も消防署員も各地の住宅地図を片手に走り回っていました」(渡辺氏)

「協定の内容は『地図を備蓄してください』というだけではありません。有事の際には各地図のコピーを自由に取っていただいて結構ですよ、という内容も含まれています」(山本氏)
「なるほど、本来はゼンリンの著作物ですから、コピーして利用するにも料金が発生するはずです。これをフリーにするというのは我々支援する側としてはありがたいことです」(渡辺氏)
ゼンリンの提供する地図セットには『複製ライセンス証』という書類が同封されている。有事の際、自治体の長、つまり市長や町長、村長がサインするだけで一定期間コピーがフリーになるのだ。
「現在全国に自治体は1740以上あります。これら全部と協定を結ぶ予定なのですか?」(渡辺氏)
「やりますよ」(山本氏)
「“ぶら防”に書いても大丈夫?」(渡辺氏)
「大丈夫です(笑い)」(山本氏)
災害時に地図を利用してほしい。だから無償で提供する。これは使命としてやっている。しかし、そうしたやり取りからは様々な『利益』を吸収することができると山本氏は言う。
「災害時に地図を提供する我々の側として、その時々はいつも手探りだったわけです。しかし、協定のためにヒヤリングを続けていくと、各地域の災害の特色が見えてきました。つまり同じ地図にしても各地域では何に備えたいのか、ニーズがまちまちなのです」(山本氏)
つまり津波に備えたい地域、台風に備えたい地域、土砂崩れ、河川の氾濫などなど。各地の地形、気象条件で変わってくる。こうしたニーズが分かっていると、どんな地図を提供すればいいのか分かってくる。
「こうした知見が蓄積されていくことで、地図会社としての奥行きが出てくるのです。協定そのものは社会貢献のためという大前提がありますが、これを続けて知り得た情報を分析することでよりよいサービスへとつなげていくことができると考えています」(山本氏)

宝の山の次の生かし方
「ゼンリンの地図を見ていて思うのですが、我々が地域の被害予測を行う場合、地域の地形図を広げて、海岸から何メートルだとか、河川から何メートルだとか、海抜はどのくらいだとか、地形から類推して『だったらこのあたりは津波がきたら水没だな。大雨が降ったら水に浸かるな』というふうに予測していくわけです。しかし、例えば航空写真にゼンリンの住宅地図を重ね合わせればもっと詳細な被害予測を作ることができると思うのです」(渡辺氏)
「NTT空間情報さんとのコラボレーションで、航空写真に住宅地図を重ねることは実際にやっていました。だから不可能ではありませんね」(山本氏)
「何が言いたいのかというと、足で情報を集めるゼンリンであれば、ここに建っているビルが何階建てであるかとか、もっというと1981年に耐震構造の法律が変わり、それ以前は旧耐震、以降は新耐震になった。ビルの竣工年数が分かれば、そうしたことまで地図上に表現することができる。だから震度いくつが起こればこのビルは倒れる可能性がある、など予測可能になるということです」(渡辺氏)
「個人情報の問題があるので公開するのかは別にして、可能ですね。例えば東日本大震災のあと、我々の調査スタッフに被災地の海岸沿いをすべて歩かせました。なにをしたのかというと、津波がどこまできたのかを実際の被害状況と聞き取りで詳細に調査をしたのです。これは公開はしていませんが、地図の上では住宅地図帳に津波がここまできた、と線を引いたものを持っています。こうした情報も重ねれば、さらに詳細な被害想定が可能になってくると思います」(山本氏)
『会社全体が地図マニア』。そんな印象のゼンリン。東京本社の入り口には全国の住宅地図が並べられている。
これを見て”防災の鬼”渡辺実氏も大喜び。
「おい、ちょっと写真を撮ってよ」
と両手を広げ、その壮観さをたたえた。

取材を終えてお世話になった山本氏へ声をかけた。
「本当にこれは宝の山。阪神大震災のときも、これを買ってきて頁を破り取ってつなげ、大きな地図を作りました。デジタルの時代になって地図の見方、使われ方は変わったとしても、地図そのものの形は変わりません。日本の平和のため、地域の防災のため、ゼンリンには今後も頑張っていただきたい。よろしくお願いします。」(渡辺氏)

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。











