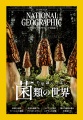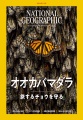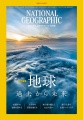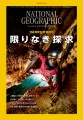外来生物は世界中で猛威を振るい、自然の生態系を脅かしている。特に蚊、ヘビ、コイなどの外来種は、既存の技術で駆除することができない。“遺伝子ドライブ(gene drive)”と呼ばれる新たな遺伝子操作技術が、国際研究チームによって発表された。外来種の遺伝子を操作することで、個体数の激減が期待されている。
「遺伝子ドライブの技術によって外来種を絶滅させ、もとの生態系を取り戻すことが可能になるだろう」と、7月17日付で「Science」誌とオンライン科学誌「eLife」に掲載された論文を執筆したハーバード大学の遺伝子工学者、ケビン・エスベルト(Kevin Esvelt)氏は述べる。
「人類と自然界が直面している問題を解決するために、この技術が責任を持って利用されるよう見届けなくてはならない」と同氏は言及している。
◆操作の仕組み
この技術は、殺虫剤に対する抵抗力を低減し、繁殖能力を妨げ、あるいは対象となる種に望ましい影響を与える遺伝子の変異を特定することから始まる。
外来種のゲノムにその変異を挿入するのだが、次世代に遺伝するという保証はない。そこで、遺伝子ドライブが登場する。基本的に遺伝子ドライブは、改変された情報を個体群に“運ぶ(ドライブする)”運転手のような役割を果たすとエスベルト氏は説明する。
ほとんどの動物には2つの異なるバージョンの遺伝子が備わっており、それぞれが五分五分の確率で次世代へと受け継がれる。
つまり、遺伝子ドライブはちょっとした不正を働いて、改変された遺伝子要素を子孫に伝播しやすくするのだ。
◆遺伝子工学の歴史
遺伝子ドライブという発想自体は新しいものではなく、1940年代までさかのぼる。
何が新しいかと言うと、クリスパー(CRISPR: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)と呼ばれる革新的な技術で、その応用によってゲノム中の特定要素に的を絞ることが可能になる。
実際、どのようにして外来種の絶滅を誘発するのだろう?
性別を決定する遺伝子を改変して、子孫がオスになる確率を高くする方法がある。もう1つは、繁殖に必要な遺伝子を不能にするという方法である。
◆実質的な応用
この技術が抱える唯一の限界は、性交を通じて繁殖する種にのみ応用が利き、かつ繁殖のサイクルが短いことが必須だ(人間の場合、世代間の時間が長いため、遺伝子ドライブは有効に働かない)。
実用化に向けて、マラリアを媒介する蚊の駆除を主な目的として開発が進められているが、実験は研究室内に制限されている。自然界で応用されるまで、あと2、3年はかかるだろう。
ハワイでは、19世紀に侵入した蚊を駆除するため、遺伝子ドライブを活用した早急な対策が必要とされている。その外来種は鳥類に感染するマラリアを媒介し、野鳥の多くはすでに絶滅、あるいは絶滅の危機に追い込まれた。温暖化によって蚊の生息域が北上すると、貴重な野鳥が生き残る高緯度の地域にまで侵入すると考えられる。
◆潜在的落とし穴
どんな技術にもリスクが伴う。
「もし遺伝子操作された種が在来の近縁種と交配した場合、改変された遺伝子とそれに関連した遺伝子ドライブも伝播する可能性がある」と指摘するのは、この研究には参加していないインペリアル・カレッジ・ロンドンの遺伝学者オースティン・バート(Austin Burt)氏だ。
ひとたび自然界に放たれると、改変された遺伝子はさらに変異する可能性もある。
「Science」誌掲載論文の共著者でアリゾナ州立大学の進化生物学者、ジェームズ・コリンズ(James Collins)氏によると、この技術が確立される前に、それがもたらす倫理的、法律的、そして社会的な影響を社会全体として考慮する必要がある。
「われわれが望まない、予期せぬ結果が生じるかもしれない」と同氏は懸念している。
Photograph by CDC/PHIL. Corbis
「遺伝子ドライブの技術によって外来種を絶滅させ、もとの生態系を取り戻すことが可能になるだろう」と、7月17日付で「Science」誌とオンライン科学誌「eLife」に掲載された論文を執筆したハーバード大学の遺伝子工学者、ケビン・エスベルト(Kevin Esvelt)氏は述べる。
「人類と自然界が直面している問題を解決するために、この技術が責任を持って利用されるよう見届けなくてはならない」と同氏は言及している。
◆操作の仕組み
この技術は、殺虫剤に対する抵抗力を低減し、繁殖能力を妨げ、あるいは対象となる種に望ましい影響を与える遺伝子の変異を特定することから始まる。
外来種のゲノムにその変異を挿入するのだが、次世代に遺伝するという保証はない。そこで、遺伝子ドライブが登場する。基本的に遺伝子ドライブは、改変された情報を個体群に“運ぶ(ドライブする)”運転手のような役割を果たすとエスベルト氏は説明する。
ほとんどの動物には2つの異なるバージョンの遺伝子が備わっており、それぞれが五分五分の確率で次世代へと受け継がれる。
つまり、遺伝子ドライブはちょっとした不正を働いて、改変された遺伝子要素を子孫に伝播しやすくするのだ。
◆遺伝子工学の歴史
遺伝子ドライブという発想自体は新しいものではなく、1940年代までさかのぼる。
何が新しいかと言うと、クリスパー(CRISPR: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)と呼ばれる革新的な技術で、その応用によってゲノム中の特定要素に的を絞ることが可能になる。
実際、どのようにして外来種の絶滅を誘発するのだろう?
性別を決定する遺伝子を改変して、子孫がオスになる確率を高くする方法がある。もう1つは、繁殖に必要な遺伝子を不能にするという方法である。
◆実質的な応用
この技術が抱える唯一の限界は、性交を通じて繁殖する種にのみ応用が利き、かつ繁殖のサイクルが短いことが必須だ(人間の場合、世代間の時間が長いため、遺伝子ドライブは有効に働かない)。
実用化に向けて、マラリアを媒介する蚊の駆除を主な目的として開発が進められているが、実験は研究室内に制限されている。自然界で応用されるまで、あと2、3年はかかるだろう。
ハワイでは、19世紀に侵入した蚊を駆除するため、遺伝子ドライブを活用した早急な対策が必要とされている。その外来種は鳥類に感染するマラリアを媒介し、野鳥の多くはすでに絶滅、あるいは絶滅の危機に追い込まれた。温暖化によって蚊の生息域が北上すると、貴重な野鳥が生き残る高緯度の地域にまで侵入すると考えられる。
◆潜在的落とし穴
どんな技術にもリスクが伴う。
「もし遺伝子操作された種が在来の近縁種と交配した場合、改変された遺伝子とそれに関連した遺伝子ドライブも伝播する可能性がある」と指摘するのは、この研究には参加していないインペリアル・カレッジ・ロンドンの遺伝学者オースティン・バート(Austin Burt)氏だ。
ひとたび自然界に放たれると、改変された遺伝子はさらに変異する可能性もある。
「Science」誌掲載論文の共著者でアリゾナ州立大学の進化生物学者、ジェームズ・コリンズ(James Collins)氏によると、この技術が確立される前に、それがもたらす倫理的、法律的、そして社会的な影響を社会全体として考慮する必要がある。
「われわれが望まない、予期せぬ結果が生じるかもしれない」と同氏は懸念している。
Photograph by CDC/PHIL. Corbis